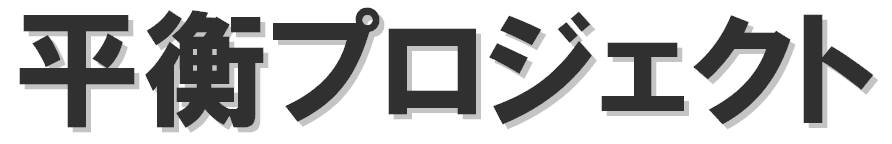
■■■平衡型FET差動+トランス式ライン・バッファ■■■
Balanced Line Buffer with Line Transformer

試作1号機
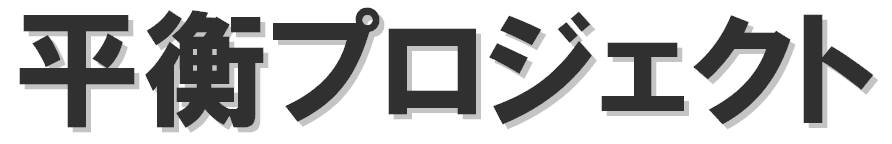
■■■平衡型FET差動+トランス式ライン・バッファ■■■
Balanced Line Buffer with Line Transformer

試作1号機
この種のラインレベルの送り出しに関してはいまだこれがベストである、という定着した方式がなく、プロ機材においては基板ユニットごとオプション扱いになっていることがあります。たとえば、我が家にあるOtariのマスターレコーダーにしても、STUDERのCDプレーヤにしても、基本仕様では最も廉価かつ物理スペックが良くなるOPアンプ仕様のものが実装されていて、別にお金を払ってオプション指定するとライントランスを使ったユニットに交換される、という風に。自作オーディオをされる方は「えっ、いまどきトランスなんか使うんですか?トランスなんか使ってカマボコ特性になりませんか?」と思われるかもしれませんが、業務用のライントランスの特性はそれはそれでノウハウがあるようで、ばかにできません。もちろん、トランスはコストが高いために採用される場面はどんどん減ってきてはいますが、お金が許すのであればトランスはむしろ歓迎される傾向にあります。そのトランスをたっぷり使った機材で録音された作品が2012年の今でも堂々レコ芸の特選盤になるわけですから、我々の浅知恵ごときでものごとを判断してはいけないようです。この実験は、ライブやレコーディングの現場で使用する汎用のラインバッファを決めるのが目的のひとつです。都内のある大手音響サービス会社のエンジニア諸氏からも相談を受けており、いろいろなものを試作して現場で使ってもらって、プロのエンジニア達の意見を聞くための前準備でもあります。次のステップでは、実用に耐えるユニットとして試作機を何台か作り、まずは我が家で試験運転します。
もうひとつの目的は、まだ製作に至っていない自宅用の平衡型ラインプリアンプで使用するラインバッファ用としての模索です。パワーアンプへモニター出力と、メインレコーダーとして使っているProToolsやOTARI MX-50Nへの送り出しの2系統の出力が必要なので、ラインバッファも2系統すなわち都合4台必要になります。
バランス伝送を行う時、入出力モードで平衡/不平衡が自由に扱えるラインアンプがあると重宝します。これまで、FET差動回路を使った純電子式のライン・バッファ・アンプの実験をしてきましたが、ここでちょっと脇道にそれてトランス式についても実験をしてみることにしました。といっても、回路を全面的に変更するのではなく、FET差動回路を使ったライン・バッファに出力部分にライン・トランスを割り込ませるだけの変更です。出力部分にトランスを使うことで、平衡/不平衡の制約がなくなります。トランスを使うことによるディスアドバンテージもあるわけですが、まあ、やってみようということです。実験回路は以下のとおりです。電源には、市販の普及の廉価版のスイッチング電源式のACアダプタを使います。初段は、2SK117による差動PPで共通ソース側は3mAの定電流回路です。定電流回路には、Idssが約1.5mAの2SK30Aを2本並列にしたものを使いました。初段の利得は31〜32dBです。その後ろには2SC4408によるエミッタフォロワが続きます。エミッタフォロワの負荷はコレクタ電流を流すための2本の抵抗(Ry=820Ω)とトランスの両方が並列になります。負帰還はトランスの2次側から初段ゲートにかけています。負帰還抵抗(56kΩ)には必要に応じて位相補正コンデンサ(Cx)を抱かせます。反転増幅器なのでこの位相補正は非常に利きがいいです。
2号機では、ライントランスの1次側にあるCTを使うことができたので、回路は右下のように変更しました。
調整箇所は、初段差動FETのソース側に入れた半固定抵抗器のみです。ライン・トランスの1次巻き線にはDC電流を流すわけにはゆきませんので、この半固定抵抗器を調節して回路図上のA点〜B点間の電圧がゼロ(1mV以下)となるようにすれば完了のはずだったのですが、当初、10Ωを取り付けていて調整可能はバイアスの範囲は15mVしかありませんのでこれでは不足でした。1号機ではドレイン抵抗値をすこしだけいじるというズルをしてかろうじてDCバランスを確保しています。この点については2号機では100Ωのものに変更しています。上の回路図は変更後のものです。
内部のレイアウトはこのようになっています(下画像)。左側が入力で、キャノン(メス)とTRSの両方が使えるNEUTRIKのコンボジャックを使いました。アンバランス入力の場合は、RCA→TRS変換プラグを使えば簡単に変換されます。右側の出力側はごく普通のキャノン(オス)です。シャーシは、奥沢で扱っている150mm×250mm×55mmのアルミ箱です。実装されているトランスはST-53Aです。両足をラグ端子のところで折り曲げてハンダづけしていますが、そのままではハンダが乗らないので、サンドペーパーで塗装を落としています。リード線の位相を間違えると低域で発振するのですぐにわかります。
平ラグのパターンは以下のとおりです。
使用部品で注意するポイントとしては、位相補正用コンデンサの選択です。いまどき、数十pFくらいの容量のコンデンサというとセラミックコンデンサしか手に入りません。音響特性が優れたディップマイカコンデンサもあるところにはありますがはなはだ高価です。コンデンサはすべての特性は完璧なものは存在しないので、温度依存性や電圧依存性など目的に応じて何を重視するか非常に細かく区別して製造されています。セラミックコンデンサの中には電圧依存性の高いものがあり、印加した電圧によって容量が著しく変化します。このようなコンデンサを数V以上の信号を扱うオーディオ回路で使うと、信号波形に応じて容量が変化し伝達特性が変化するために音に色付けが生じます(下図中のF特性)。本機では、印加する電圧によって容量が変化しないCH特性のもの(ムラタRPE2Cシリーズ)を選んで使用しています。
出典:http://www.murata.co.jp/products/catalog/pdf/c72.pdf
以下の実験データは、組み立てた平ラグユニットを、上記のシャーシに組み込む前に別の実験シャーシに取り付けて行ったものです。<Sansui ST-53A>
これは、SansuiのST-53Aを組み込んだ時の特性です。Ry=820Ω、負荷(RL)は600Ω、位相補正コンデンサ(Cx)には22pF/32pFを当てています。位相補正なしですと約170kHzできれいに発振してくれます。10pF〜47pFの間でいろいろと試してみましたが、最終的には22pF〜33pFあたりに落ち着きそうです。負荷(RL)を1kΩにすると150kHzあたりに山ができますので、600Ωの負荷抵抗の存在は重要であり、出力をオープンにする使い方はできません。
周波数特性は、太線がCx=22pFで、細線がCx=32pFのデータです。22pFの時の方が良さそうに思えますが鋭いオーバーシュートが出ており、波形は32pFの方がきれいです。トランスを使わない回路の場合は周波数特性と方形波形とはきれいな相関を見せますが、トランスを使った回路では実際に波形を追ってみないと何が起きているかわかりにくいように思います。
こちらのデータを見ていただくとわかりますが、ST-53Aは1kHz以下の領域で周波数が低くなるほど歪みがどんどん増加する弱点があります。しかし、強めの負帰還がかけてあるために、仕上がりの歪み率はさほど悪くありません。50Hzにおいても1%歪みで4Vが得られており、最大出力電圧では100Hz以上の帯域と遜色ありません。700円の廉価トランスも、うまく使ってやれば結構まともなオーディオアンプになるということなのでしょうか。
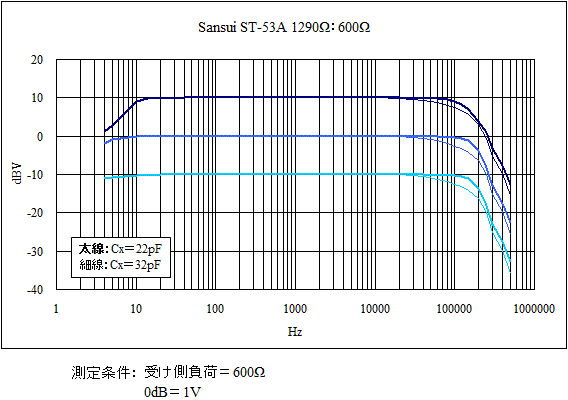
<Sansui ST-92>
今度は、SansuiのST-92を組み込んだ時の特性です。Ry=820Ω、負荷(RL)は600Ω、位相補正コンデンサ(Cx)には22pF/32pFでST-53Aの時と同じです。
周波数特性は、22pFでは80kHzあたりで山ができており、32pFでようやく大人しくなります。高域側の減衰の肩特性がくこれうらいですとオーバーシュートが出ますので、Cxの値は32pFでは不足で39〜47pFくらいが適切です。歪み率特性は、ST-53Aとほぼ同等と思っていいでしょう。
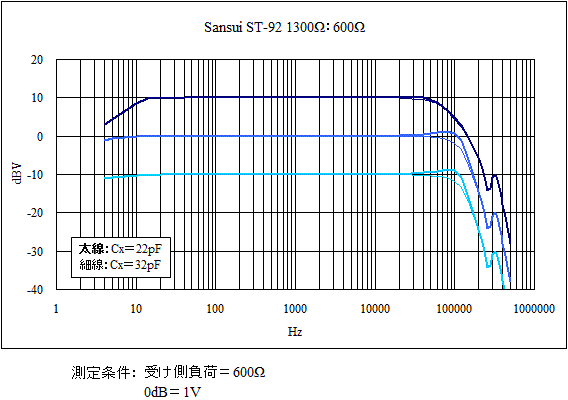
<東栄 600Ω:600Ω>
東栄変成器で出している600Ω:600Ωのトランスはセンタータップがあるので、回路を変更して当初はRz=390Ωとしました。この時のコレクタ電流は17.7mA×2です。しかし、このトランスは1次インダクタンスが小さいため、200Hz以下の帯域で十分な負荷インピーダンスが得られません。実験回路にそのまま組み込むと低い周波数で最大出力電圧が得られなくなります(左下)。そこで、Rz=195Ωとしてコレクタ電流を33.3mA×2に増やしたのが右下のデータです。100Hz以下でも出力が落ちなくなりましたが、1V以下の領域での低域の歪の多さは変わりません。。
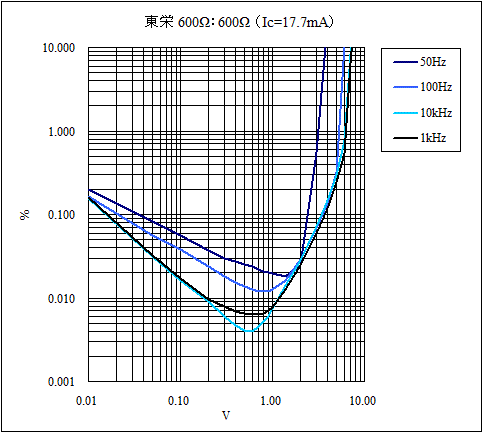
周波数特性は以下のとおりですが、位相補正コンデンサ容量は手持ちの都合で22pFとしたため、高域側の減衰の肩がややいかっています。最適値は27pFあたりだと思います。
<TAMRA TD-1W>
お次はTAMRAのTD-1(W)です。Rz=390Ω、負荷(RL)は1kΩ、位相補正コンデンサ(Cx)は22pFで最も少ないです。
データを見ていただければわかりますので、解説は要しないでしょう。周波数特性はとても素直で波形もきれいです。特筆すべきは歪み率特性で、50Hzから10kHzまでぴったりと重なりました。こんな見事な特性は過去見たことがありません。いやー、参りました。
なお、上記の2つのケースと比べて最大出力電圧が高いのは、巻き線比が1:1であるためで、これはTD-1Wが優れているわけではありません。残念ながらSansuiのSTシリーズには巻き線比が1:1でコアサイズが大きなのものがないのです。最大出力電圧を稼ぎたかったら、アンプ部の電源電圧をもっと高く設定することになります。TD-1WのWはWireWrapping仕様の意味で、タムラのカタログに載っているのは通常端子タイプのTD-1で中身は同じです。
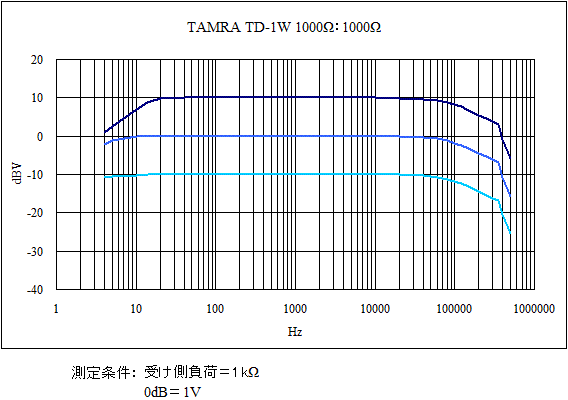
<TAMRA TF-3>
お次はTAMRAのTF-3です。Rz=390Ω、負荷(RL)は600Ωです。
周波数特性はてこずりました。エミッタ抵抗(27Ω)の値を大きくしてやればもっと大人しくなるのではないかと思いましたが、とりあえず同一条件でデータを取りました。Cxの値は29pFと32pFの2パターンです。容量をこれ以上大きくすると20kHz減衰が始まってしまうので、ぎりぎりのポイントを探してみたわけです。実際の製作でしたら33pFを使うことになります。歪み率特性はこのトランスも見事なもので、TD-1Wの時よりもさらにきれいに揃っています。
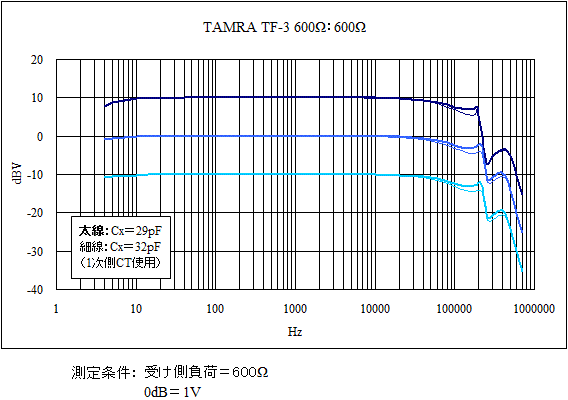
この種の目的の回路を設計する際に注意しなければならないことに、出力信号の平衡度の問題があります。平衡度とは、2つのバランス出力端子に現れる信号が、アースからみてどれくらい平衡であるか、簡単にいうとアースを基準に測定して同じ電位であるか、またインピーダンス的にみても同じ条件か、という問題です。実験回路は、入出力ともにバランスであれば平衡度は問題ありませんが、入力のCOLD側をアースしてアンバランス入力とした場合、出力側の平衡度が低下します。対アース電圧で、HOT側とCOLD側とで7〜8%くらいの差が生じます。こうなる原因は、アンバランスとして使った場合に負帰還抵抗のバランスが崩れることにあります。この様子を説明したのが下図です。
←作成中
上側の負帰還ループは、47kΩと56kΩのつなぎ目のところはイマジナリーショートになるのでほぼアースされていると考えていいのですが、下側の負帰還ループは、47kΩと56kΩが直列になったものとみなせます。これを出力側からみると、上側は56kΩでアースされ、下側は103kΩでアースされていることになり、これが原因で平衡度を下げているわけです。
アンバランス入力として使った場合でも出力側の平衡度を高めるには、上記の負帰還抵抗よりも十分に小さな抵抗をHot/Cold両出力とアースとの間に入れる必要があります。実験回路では、負帰還抵抗値が47kΩおよび103kΩであるのに対して、Hot/Cold両出力とアース間の抵抗が10kΩと十分小さくないことがまずかったわけです。ちなみに、この2個の10kΩをはずすと平衡度はさらに悪化します。下の表は、抵抗値によって1V出力における平衡度がどう変化するかをまとめたものです。
Hot/Cold〜アース間の抵抗 なし 10kΩ 6.2kΩ 2.4kΩ 1.2kΩ Hot〜Cold間 1000mV Hot〜アース側 648mV 518mV 512mV 505mV 502mV Cold〜アース側 352mV 482mV 488mV 495mV 498mV 偏差 83.9% 7.4% 4.8% 1.9% 0.97% 5%の平衡度を狙うには6.2kΩ以下にすればよく、2%以下を狙うであれば2.4kΩ以下にすればいいことになります。しかし、この抵抗値をあまり小さくすると負荷が重くなってしまうのと、もうひとつ、出力側をバランスで使うかアンバランスで使うかで負荷が変わってしまうという問題が生じます。回路をうまくまとめるためには、ことさらに平衡度ばかり追わないことです。