定電流回路とは
「定電流回路」とは、その両端にかかる電圧の大小にかかわらず、つねに一定の電流が流れる回路のことです。抵抗であれば、その両端にかかる電圧が変化すれば、そこに流れる電流もその変化量に比例して変化します。理想的な定電流回路では、その両端にかかる電圧が変化しても、そこに流れる電流の変化量はゼロです。そのため、動作中の定電流回路の両端に信号電圧を与えても、定電流回路には信号電流は流れません。すなわち、インピーダンスは無限大(∞)ということになります。定電流回路は、直流は流したいが、信号は遮断したいような場合に非常に便利です。
定電流回路のこのような性質は、増幅回路では、無限大の値を持った負荷抵抗として利用されたり、差動増幅回路の共通カソード(エミッタ)の定電流源として使われます。
定電流回路・・・5極管
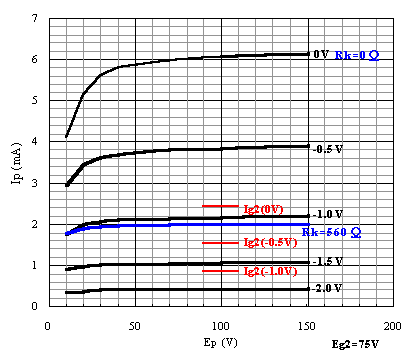 差動増幅回路を理解し、設計できるようになるためには「定電流回路」について十分に理解しなければなりません。
差動増幅回路を理解し、設計できるようになるためには「定電流回路」について十分に理解しなければなりません。右図は、5極電圧増幅管6AU6のEp-Ip特性(実測)です。いちばん上のEg1=0Vのカーブに着目してください。プレート電圧(Ep)が10Vの時のプレート電流(Ip)は4.2mAですね。Epが40Vに上昇するとIpも5.8mAに増加しますが、そこから先はEpを高くしていっても、Ip値はあまり増加しません。Ep=40〜150Vの範囲で、Ip=5.8〜6.1mAの間でほぼ一定になります。このように、回路の両端にかかる電圧の大小にかかわらず、つねに一定の電流が流れるような性質のことを「定電流特性」といいます。ただし、カソード側には、このIpとスクリーングリッド電流の合計値が流れますので、これは別に考えます。
さて、Epが40Vから150Vまで110Vの変化をした時に、Ipは5.8mAから6.1mAまで0.3mAの変化をしたわけですから、これをオームの法則にあてはめてみると、110V÷0.3mA=366.7kΩという値が得られます。これが、定電流回路の内部抵抗です。(実際には、Epの値によって傾き=内部抵抗値は一定ではありません。)
今度は、なかほどのEg1=-1Vのカーブ付近に着目してみます。Ep=150Vの時、Ip=2mAとなるようなEg1の値は、だいたい-1.1Vくらいに読み取れます。この時のスクリーングリッド電流は、図の赤線より、おおよそ0.9mAです。すなわち、1.1Vの電圧降下を生じさせるようなカソード抵抗の値は1.1V÷2.9mA=379Ωになります。
そこで、379Ωに近い値ということで、390Ωのカソード抵抗を入れた場合のEp-Ip特性を求めてみると、図中の青線が得られました。これが、390Ωのカソード抵抗を入れた6AU6の定電流特性です。前述したEg1=0Vの時と比べて、広い電圧の範囲にわたって安定した定電流特性が得られている様子がわかると思います。
定電流回路の一般的性質として、印加される電圧がある一定値以下になると、定電流特性はどんどん失われます。6AU6の場合では、40V以下の領域では、定電流特性は得られません。
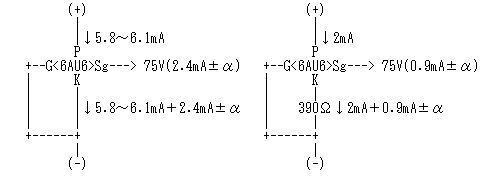 これまでのところを回路図にすると、右図のようになります。カソード抵抗がない(Rk=0Ω)場合が左側、390Ωのカソード抵抗を入れた場合が右側です。このように、5極管を使った定電流回路では、カソード抵抗の値を変化させることによって、定電流特性を連続的に変化させることが可能です。また、カソード抵抗の値が高い方が、より優れた定電流特性を得ることができます。
これまでのところを回路図にすると、右図のようになります。カソード抵抗がない(Rk=0Ω)場合が左側、390Ωのカソード抵抗を入れた場合が右側です。このように、5極管を使った定電流回路では、カソード抵抗の値を変化させることによって、定電流特性を連続的に変化させることが可能です。また、カソード抵抗の値が高い方が、より優れた定電流特性を得ることができます。
但し、スクリーングリッド電流は定電流特性にはなりませんので、スクリーングリッドの電源だけは定電流回路から独立させて、供給しなければなりません。
定電流回路・・・FETと定電流ダイオード(CRD)
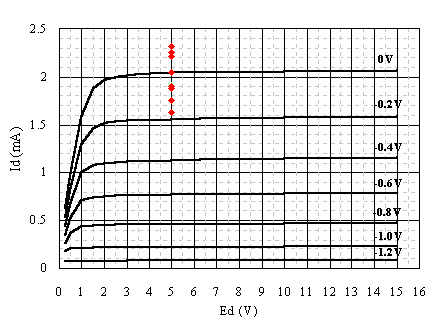 5極管と非常に良く似た性質を持つFETは、5極管以上にすぐれた定電流特性を持っています。
5極管と非常に良く似た性質を持つFETは、5極管以上にすぐれた定電流特性を持っています。右図は、2SK30A(Yクラス)の特性の実測データです。2SK30Aという名前がついていても、個体ごとのIdss(ゲートのバイアスが0Vの時のドレイン電流)は相当なばらつきがありますが、これはYクラスのものの実測特性です。同じYクラスでも、Idssはまだばらつきがあり、その様子を赤印でプロットしてあります。
ごらんのとおり、ドレイン〜ソース間電圧が4V以上の領域では、非常にすぐれた定電流特性を持っていることがわかります。さきほどの5極管では、定電流得特性はプレートが50V以上にならない得られませんでしたから、FETがいかに低い電圧でも定電流素子として使えるかおわかりいただけると思います。
ただし、2SK30Aのような小型のFETで気をつけなければならないのは、ドレイン〜ソース間電圧をあまり高くとれないということです。6AU6であれば、150V以上の電圧をかけて、4mA以上の電流を流すことができます。この時のプレート損失は、150V×4mA=0.6Wとなりますが、6AU6の最大プレート損失はもっと大きな値であり、十分な余裕があります。
しかし、豆粒のような2SK30Aでは、25Vの電圧に2mAの電流・・・すなわち、25V×2mA=50mWの損失を与えただけで、かなりの温度上昇になるだけでなく、温度によるドリフトが生じてしまいます。それに、50V以上の高い電圧をかけたならば、素子が破壊してしまいます。
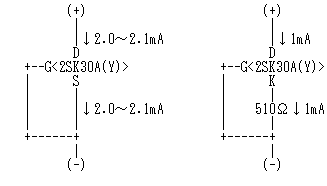 右図は、FET(2SK30A-Yクラス)を使った場合の定電流回路の例です。右図(左)の回路は、単にゲートとソースをつないだだけのものですが、これで右上の図でいうと、ゲート電圧=0Vの特性になります。
右図は、FET(2SK30A-Yクラス)を使った場合の定電流回路の例です。右図(左)の回路は、単にゲートとソースをつないだだけのものですが、これで右上の図でいうと、ゲート電圧=0Vの特性になります。
ソース側に抵抗を挿入してバイアスをかけてやると、その抵抗値を変化させることによって、任意の定電流特性を得ることができるようになります。右図(右)の回路では、510Ωの抵抗を入れていますが、これでほぼ1mAの定電流特性になります。
最近では、定電流ダイオード(CRD)が容易に入手できるようになりました。定電流ダイオードの内部構造はFETと同じで、内部的にゲートがソースに接続されており、その内部構造は右図(左)の回路と同じです。外見は2つの端子を持ったダイオードになっています。
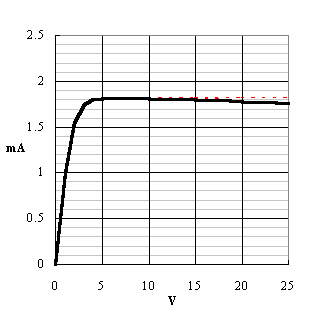 右図は、2mAの定格を持った定電流ダイオードの実測特性です。さきほどの、2SK30A(Yクラス)の特性データと非常に良く似ており、4V以上から定電流特性になるというところまで同じです。定電流特性が2mAではなく1.8mAくらいであるというのは、単に、ばらつきが原因です。2mAの規格の定電流ダイオードでは、1.7mA〜2.3mAくらいのばらつきがあります。
右図は、2mAの定格を持った定電流ダイオードの実測特性です。さきほどの、2SK30A(Yクラス)の特性データと非常に良く似ており、4V以上から定電流特性になるというところまで同じです。定電流特性が2mAではなく1.8mAくらいであるというのは、単に、ばらつきが原因です。2mAの規格の定電流ダイオードでは、1.7mA〜2.3mAくらいのばらつきがあります。
ところで、右図では、電圧が10Vを越えたあたりから、電流値が徐々に減少しはじめています。これは何故なのでしょうか。中身がFETである以上、定電流ダイオードも温度変化に対してかなり敏感なところがあります。2mAの定電流特性を持った定電流ダイオードに25Vの電圧をかけると、25V×2mA=50mWの電力を消費しますが、これくらいの消費電力になると流れる電流の値が数%程度減少してきます(右図のケースでは-2.2%)。これは、定電流ダイオードが負の温度依存特性を持っているためです。
定電流特性そのものは、印加する電圧が高くなっても、電流値が減少するようなことはありません。むしろ、わずかずつですが増加します(赤い点線)。ですから、ダイオードが自己発熱の影響を受けないような環境(強制冷却やごく短時間の測定)では、このような現象は生じません。FETも定電流ダイオードも、設計どおりの正確で安定した動作をさせるためには、印加する電圧は4V以上で15V以下の範囲にとどめるのがよいと思います。
もっと高い電圧でも安定した定電流特性が必要な場合は、前述したような5極管を使うか、以下に述べような3極管と定電流ダイオードを組み合わせた回路を使います。
定電流回路・・・3極管+定電流ダイオード(CRD)
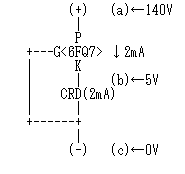 2mAの定電流特性で、150Vの電圧に耐える定電流回路について考えてみます。冒頭に述べたように、6AU6のような5極管を使えば、150V、2mAの定電流回路は可能です。しかし、スクリーン・グリッド電流を調達しなければならないため、実装面では電源回路が複雑になってしまいます。ここでは、3極管と定電流ダイオードを使った、非常にシンプルかつ高性能の定電流回路をご紹介します(右図)。
2mAの定電流特性で、150Vの電圧に耐える定電流回路について考えてみます。冒頭に述べたように、6AU6のような5極管を使えば、150V、2mAの定電流回路は可能です。しかし、スクリーン・グリッド電流を調達しなければならないため、実装面では電源回路が複雑になってしまいます。ここでは、3極管と定電流ダイオードを使った、非常にシンプルかつ高性能の定電流回路をご紹介します(右図)。ごらんのとおり、3極管のグリッド〜カソード間に定電流ダイオードを入れただけの簡単な回路です。これで立派に高耐圧定電流回路として動作します。しかも、定電流回路の内部抵抗は元の定電流ダイオードの内部抵抗のμ倍になり、これはちょっとやそっとでは得られないくらい高い値になります。また、端子間容量は、3極管のCg-pとほぼ同じになりますが、この値は、定電流ダイオードの本来の容量よりも相当に低い値です。
このように、ほとんど理想的ともいえる定電流回路ではありますが、ひとつだけ欠点があります。それは、低い回路電圧では動作しないということです。この回路では、定電流ダイオードの動作電圧は3極管のバイアス電圧に等しくなりますから、3極管のバイアスが-4Vよりも深い動作の領域でないとこの回路は期待されるような動作をしません。
6FQ7を使い、2mAの定電流ダイオードと組み合わせた時の、この回路の特性をEp-Ip特性上で表現したのが右下図です。その時の、(a)〜(b)間電圧と各部の動作の様子を以下にまとめてみましたので、参考にしてください。
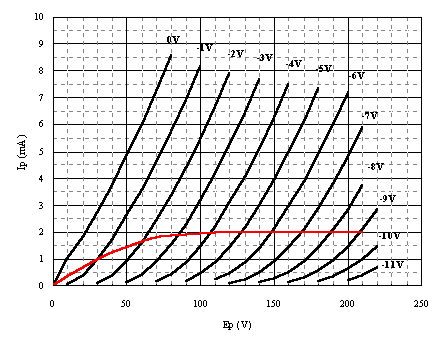
| (a)〜(b)間電圧 | (b)〜(c)間電圧 (=6FQ7のバイアス) | (a)〜(c)間電圧 | 定電流特性 |
|---|---|---|---|
| 80V | 2.6V | 82.6V | × |
| 100V | 3.6V | 103.6V | △ |
| 120V | 4.6V | 124.6V | ○ |
| 140V | 5.6V | 145.6V | ○ |
(a)〜(c)間電圧が100V程度以下では、定電流ダイオードが定電流特性を発揮できるだけの動作電圧、すなわち、6FQ7のバイアス電圧が得られません。この回路を生かすには、内部抵抗が低く、かつ、μが低い3極管が適しています。定電流ダイオードの動作電圧4Vが確保できるバイアスを基準として、各種3極管・定電流特性・最低動作電圧の関係を以下にまとめてみました。
| 1mA | 2mA | 4mA | 6mA | |
|---|---|---|---|---|
| 12AX7/ECC83 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 |
| 12AU7/ECC82 | 約85V | 約105V | 約125V | 約140V |
| 6FQ7/6SN7 | 約95V | 約110V | 約130V | 約150V |
| 5687 | 約70V | 約80V | 約90V | 約100V |
| 6DJ8/6922 | 約120V | 約135V | 約150V | 約160V |
(注:実測値によるEp-Ip特性をベースに算出していますので、他のデータによって求めた値とは、若干食い違いがあるかもしれません。)
定電流「的」回路・・・3極管+抵抗
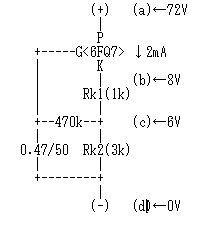 右の回路を見てください。(a)〜(d)間に72Vの電圧がかかっており、そこには2mAの電流が流れています。もし、(a)〜(c)間が1本の抵抗だったら、その値は、72V÷2mA=36kΩのはずですね。
右の回路を見てください。(a)〜(d)間に72Vの電圧がかかっており、そこには2mAの電流が流れています。もし、(a)〜(c)間が1本の抵抗だったら、その値は、72V÷2mA=36kΩのはずですね。この回路の直流動作を考えてみます。(a)〜(c)間に限っていえば、これは1kΩのカソード抵抗を持ったごく普通のカソードバイアス回路です。もし、(a)〜(c)間が1本の抵抗だったら、その値は、66V÷2mA=33kΩのはずです。(a)〜(c)間は2端子回路ですが、これは、
抵抗値 = rp(=内部抵抗) + Rk × ( μ + 1 )
で求めることができます。rp=約10kΩ、μ=約22、Rk1=1kΩを代入して計算すると、
33kΩ = 10kΩ + 1kΩ × ( 22 + 1 )
抵抗値は、33kΩとなって抵抗とみなした時の値ときれいに一致します。これに直列になっているRk2の3kΩをたして36kΩとなります。では交流的にみた場合はどうなるでしょうか。コンデンサ(0.47μF)が生きてますから、rp=約10kΩ、μ=約22、Rk1=1kΩ+3kΩになります。そこで、これを代入して計算すると、
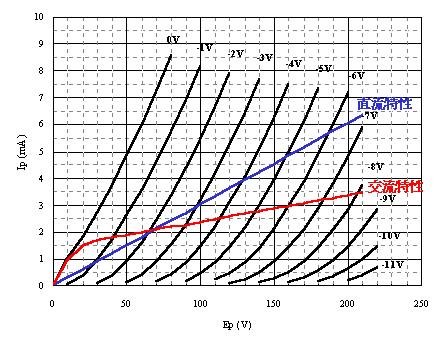 102kΩ = 10kΩ + 4kΩ × ( 22 + 1 )
102kΩ = 10kΩ + 4kΩ × ( 22 + 1 )
抵抗値は、102kΩとなりました。このような回路では、直流的には36kΩの抵抗と等価なのに、交流的には102kΩの抵抗と等価になります。つまり、交流的には、不充分ながらも定電流(的?)回路となるのです。
このような動作をEp-Ip特性上で表現したのが右図です。直流特性(青線)は、カソード抵抗値=1kΩの2端子回路の特性ですので、Ip=1mAの時のバイアスは-1V、Ip=2mAの時のバイアスは-2Vとなるような点を結んでいます。交流特性(赤線)は、バイアスが0Vの時の立ちあがり曲線と、Ep=66V、Ip=2mAのポイントで青線と交差するような102kΩの角度を持った直線との合成です。
この赤い線が、定電流「的」回路の特性にあたるわけですが、角度がついていることに目をつぶれば、定電流特性「的」な特徴を持っていることがよくわかります。Rk2の値をもっと大きくすれば、より定電流特性「的」になってゆきます。
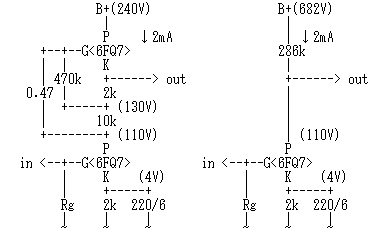 SRPP回路の応用で、μフォロワと呼ばれる回路がありますが、μフォロワ回路ではこの定電流(的?)回路をプレート側の負荷として活用しているために、通常の増幅回路よりも高い利得が得られるのです。
SRPP回路の応用で、μフォロワと呼ばれる回路がありますが、μフォロワ回路ではこの定電流(的?)回路をプレート側の負荷として活用しているために、通常の増幅回路よりも高い利得が得られるのです。
右図(左)の例では、もっぱら増幅作用を営んでいる下側の6FQ7は、Ep=106V、Ip=2mAでバイアス=-4Vの動作になっています。上側6FQ7はここでご紹介した定電流「的」回路になっていて、その2端子回路としての交流インピーダンスは、
286kΩ = 10kΩ + 12kΩ × ( 22 + 1 )
となりますので、下側管からみたら、動作条件は右図(右)と等価になります。上側管の動作条件はさておき、増幅作用の源泉である下側管の動作としては、定電流「的」負荷が与えられた場合の動作はこういうことになるわけです。
補足しますと、μフォロワ回路では、下側管のプレートに生じた出力は、コンデンサ(0.47μF)を通って上側管グリッドに入力されます。一方で、出力は上側管カソードから取り出されているため、カソード・フォロワと同じ効果が生じ、最終的な出力インピーダンスは非常に低くなります。上側管のグリッドに入力があるとすると、下側管からみたプレート負荷は286kΩ一定というわけにはゆかず、変動するのではないか、と考えたくなります。しかし、よく考えてみてください。なぜ、下側管からみたプレート負荷は286kΩのままほとんど一定になるのか。これは、皆さんへの応用問題としての宿題です。
定電流回路・・・トランジスタ
トランジスタは、単独では定電流特性を持っていませんので、他の素子と組み合わせることで定電流特性を実現します。回路が若干複雑になりますが、回路を工夫することで、高い精度、すぐれた温度安定性、高い耐圧、広範な電流特性を得ることができます。
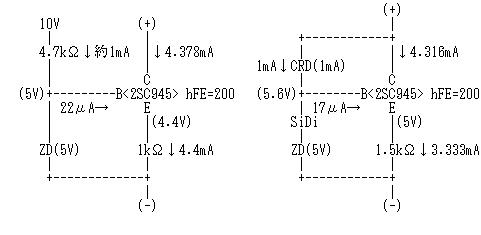 右図の左の回路が、トランジスタを使ったもっともベーシックな定電流回路です。トランジスタには、NEC製のロングセラー、2SC945を使ってみました。2SC945のhFEはおおよそ200ですから、コレクタ電流が1mAの時のベース電流は、1mA÷200=5μAになります。
右図の左の回路が、トランジスタを使ったもっともベーシックな定電流回路です。トランジスタには、NEC製のロングセラー、2SC945を使ってみました。2SC945のhFEはおおよそ200ですから、コレクタ電流が1mAの時のベース電流は、1mA÷200=5μAになります。
外部から+10V、約1mAの電源を供給し、これで5Vのツェナーダイオード(ZD)を動作させます。トランジスタのエミッタ側には、抵抗がはいっています。トランジスタのベース〜エミッタ電圧は、ほぼ0.6Vで一定とみなせますから、この抵抗の両端には、5V-0.6V=4.4Vの電圧がかかる計算になります。もし、この抵抗値が1kΩであれば、この抵抗には、4.4V÷1kΩ=4.4mAの電流が流れます。コレクタ電流は、エミッタ電流からベース電流を引いた値ですから、この回路では4.378mAの定電流回路になります。
半導体のほとんどすべては、温度依存性を持っています。ツェナーダイオードは、5Vあたりでは温度変化に対しておおむねニュートラルですが、6V以上になると温度変化に対して正の相関が現れはじめるため、温度が上昇するとともにツェナー電圧も上昇します。たとえば、10Vのツェナーダイオードでは温度1℃あたり+0.06%くらいありますから、1℃の上昇で+6mV、50℃の上昇では+0.06Vになります。反対に、トランジスタのベース〜エミッタ間電圧やシリコンダイオードの順方向電圧は、温度に対して負の相関があり、その値は温度1℃あたり-2mVです。これは、温度1℃あたり-0.33%に相当しますからばかにできません。
温度に対する安定度という点で考えると、上図左の回路はちょっと問題があります。ツェナーダイオードは5Vのものを使っていますので、温度依存性はないものとします。しかし、トランジスタのベース〜エミッタ間電圧は温度が高くなるにつれて低下するため、温度が50℃上昇した場合、-2mV×50℃=-0.1Vの低下が生じて、1kΩの抵抗の両端電圧は、4.4Vから4.5Vに上昇することになります。真空管アンプのシャーシ内部は、50℃の温度上昇くらいは日常茶飯事だということを忘れてはいけません。
この温度依存性を打ち消す操作のことを「温度補償」といいます。上図右の回路は、ツェナーダイオード(ZD)と直列にシリコンダイオード(SiDi)を入れることで、トランジスタ(2SC945)のベース〜エミッタ間電圧の温度依存性をきれいに打ち消しています。また、ツェナーダイオード側の電源供給も、定電流側から取って自己完結型とすることで別立ての電源(+10V)を不要にしています。
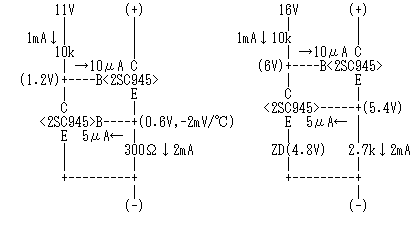 上記の定電流回路にトランジスタをもう1つ追加して、定電流特性を飛躍的に向上させ、回路インピーダンスがきわめて高くなっているのが右図の2つの回路です。
上記の定電流回路にトランジスタをもう1つ追加して、定電流特性を飛躍的に向上させ、回路インピーダンスがきわめて高くなっているのが右図の2つの回路です。
左側の回路では、ツェナーダイオードを省略したため、非常に低い動作電圧(1V以下)で稼動し、しかも、非常に高い回路インピーダンスが得られます。一方で、トランジスタのベース〜エミッタ間電圧の温度依存性(-2mV/℃)がそのまま定電流特性まで現れてきます(-6.7μA/℃)から、周囲温度が30℃上昇した場合、2mAから1.8mAまで減少します。
右側の回路では、ツェナーダイオードを追加することで、温度に対する安定度はかなり改善されている反面、6V以上でないと正常な定電流特性は得られません。
いずれの場合も、2SC945を、もっと耐圧の高いトランジスタに置き換えたり、放熱板を取り付けたパワートランジスタにすることによって、自在に高電圧・大電流化できるところがこの方式の良い点です。
