ヒーターがいらない真空管
真空管の泣き所は、そのばかにならないヒーター電力と発生する熱量、そして大きな図体です。トランジスタという「ヒーター電源のいらない、ヒーターが断線しない、半永久的(ウソです)に使える、真空管と同じ(ような)能力があるのに米粒みたいに小さな未来の増幅素子」が登場したことで、真空管はあっという間にこの世から駆逐されてしまったのでした。真空管もトランジスタも、ともに増幅機能を持っています。しかし、固有の電気的特性も、増幅回路を組んだ時の挙動も、実際にはずいぶん異なっています。真空管とトランジスタは、同じような増幅作用があり、同じようとに使われるのに、全然違う性質を持っている、という不思議な関係なのです。
真空管アンプを組む場合でも、トランジスタのお世話になることは珍しくありません。また、いくら真空管びいきな人であっても、トランジスタの基礎知識なしでオーディオ技術を語ることはできないと思います。そこで本章では、トランジスタの基本的な動作や性質についてまとめてみたいと思います。
3本の足
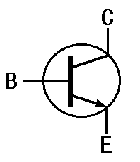 トランジスタにはふつう3本の足がはえています。それぞれ「ベース(B)」、「コレクタ(C)」、「エミッタ(E)」といい、それぞれ真空管でいう「グリッド」、「プレート」、「カソード」に対応します。回路図に描くと右図のようになります。
トランジスタにはふつう3本の足がはえています。それぞれ「ベース(B)」、「コレクタ(C)」、「エミッタ(E)」といい、それぞれ真空管でいう「グリッド」、「プレート」、「カソード」に対応します。回路図に描くと右図のようになります。
- ベース(B) = グリッド(G)
- コレクタ(C) = プレート(P)
- エミッタ(E) = カソード(K)
なお、大型の電力型トランジスタの中には足が2本しかないものもあります。そのようなトランジスタでは、金属製の本体が(例外もありますが)コレクタにつながっています。また、3本足であっても、本体が金属製であったり金属片がついていたりするものの多くは本体や金属片が中部でコレクタにもつながっていますので、不用意にシャーシなどに接触させてはいけません。4本足、5本足、6本足のトランジスタもないわけではありませんがきりがないのでここでは説明を省略します。市販のトランジスタ規格表(CQ出版社)やネット上で公開されているデータシートの形状のところを見て判断してください。
トランジスタの基本的性質
日本では、トランジスタには「2SCなんとかかんとか」、「2SAなんとかかんとか」という風に名称がつけられており、「なんとかかんとか」のところには数字が与えられています。秋葉原等で1本50円以下で簡単に入手できる「2SC1815」を教材にしていろいろみてゆこうと思います。コレクタ(C)からエミッタ(E)に向かって流れる電流のことを「コレクタ電流(IC)」と呼びます。真空管でいうプレート電流(Ip)とほぼ同じと考えてください。トランジスタでは、ベース(B)からエミッタ(E)に向かっても電流が流れます。これを「ベース電流(IB)」と呼びます。
「コレクタ」→「エミッタ」・・・コレクタ電流(IC)ところで、トランジスタにはhFEという定数があり、別名電流増幅率といいます。そして、ベース電流とコレクタ電流との間には、
「ベース」→「エミッタ」・・・ベース電流(IB)
コレクタ電流(IC) = ベース電流(IB) × hFEという関係があります。つまりコレクタ電流は、ベース電流のhFE倍流れるというわけです。2SC1815のhFEはだいたい200くらいですから、コレクタ電流が1mA流れている時のベース電流はたったの5μAです。そして、ベース電流が6μAに増加すると、コレクタ電流はベース電流のhFE倍ですから1.2mAが流れる、ということになります。
真空管では、グリッドにマイナスの電圧(バイアス)与え、このバイアス電圧を変化させると、プレート電流は増えたり減ったりしました。トランジスタでは、グリッド・バイアス電圧のかわりにベース電流を変化させることで増幅作用を行うのです。真空管が電圧増幅といわれ、トランジスタが電流増幅であるといわれるのは、このような性質の違いがあるからです。
ところで、ベースには真空管のようなバイアス電圧のようなものはないのでしょうか。トランジスタはちょっと面白い性質を持っていて、ベースとエミッタの間で一定の電圧を保ちます。2SC1815の場合ですと、ベース電圧はエミッタ電圧に対して常に約0.6V高い、という性質があります。この約0.6Vという電圧は、周囲の影響を受けますがほぼ一定で、真空管のように大きく変化させることはできません。これをベース・エミッタ間電圧(VBE)といいます。
バイアス回路
トランジスタに真空管でいえばバイアスに該当するものを与え、こちらが希望するような条件で動作させるためには、ベースに対して一定の電流(すなわちベース電流)を与えてやらなければなりません。以下のような簡単な回路で考えてみます。(このような増幅回路のことをエミッタ接地増幅回路といいますが、話が長くなるので詳しい説明は章を改めます。)下の簡単な回路でトランジスタの動作条件について検討してみましょう。電源電圧は20Vであるものとします。ベース・エミッタ間電圧(VBE)の性質から2SC945のベース電圧は約0.6Vということになりますから、RB(1MΩ)の両端にかかる電圧は、20V-0.6V=19.4Vです。RBに流れる電流は、19.4V÷1MΩ=19.4μAとなり、これがベース電流になります。2SC945のhFEが200であるとすると、コレクタ電流は19.4μA×200=3.88mAとなります。
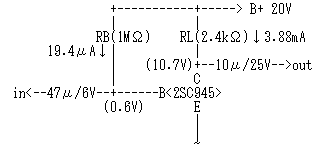 ベース抵抗1本による簡易バイアス回路
ベース抵抗1本による簡易バイアス回路
もし、B+とコレクタの間に負荷として2.4kΩの抵抗がはいっていたとすると、2.4kΩの抵抗に流れる電流は3.88mAですからここで生じる電圧は、3.88mA×2.4kΩ=9.3Vとなり、コレクタ電圧は10.7Vになって(電源電圧の1/2くらい)、増幅回路としての格好がついてきます。この状態で、ベースに交流信号を入力してやると、コレクタ側からは増幅された出力信号を取り出すことができます。ちなみに、この増幅回路の入力インピーダンスは約1.3kΩ(真空管回路に比べてずいぶん低い)で、利得は約350倍(真空管回路ではこんな大きな利得は得られない)です。以下に述べる2つに回路例も同様です。トランジスタ増幅回路の入力インピーダンスや利得の計算法は章を改めて詳説します。
hFE
ところで、トランジスタのhFEという定数は一定なのでしょうか。残念ながらそうではありません。まず、同じ名前のトランジスタであってももの大変なバラツキがあります。2SC1815の場合ですと、個体ごとに100〜400くらいにばらついています。真空管では考えられないくらい大きなばらつきです。トランジスタの製造過程でhFEをきれいに揃える、ということはできないのです。そこで一旦作ってみて、一定の範囲に収まったものについて選別し、クラス分けをしたものが市場で売られることになります。たとえば、東芝製の半導体では、O=Orangeの略、Y=Yellow、GR=Green、BL=Blue・・といったクラス分けがあり、Oクラス→BLクラスに向かってhFEは大きな値になっています。日立製では、A〜Eといったクラス分けだったように記憶します。このような事情があるため、上図のようなバイアス回路を使ってベース電流を一定にしたとしても、2SC1815のhFEが常に200であるという保証はどこにもなく、hFEが100だったらコレクタ電流は1.94mAになりますし、hFEが300だったらコレクタ電流は5.82mAにもなってしまいます。まだあります。hFEは温度にも敏感で、一般に温度が高くなるほどhFE値は増加します。加えて、コレクタ電流の多寡によってもhFE値は変化するのです。コレクタ電流の増加とともにhFE値も増加してゆきますが、コレクタ電流をどんどん多くしいって一定値を超えるとhFE値は急激に低下しいってしまうという性質も持っています。
このように、トランジスタ回路では、hFEが相当にアバウトであるために、hFE値の大小の影響を受けにくいような回路上の工夫をする、というのが常識となっています。真空管が、同じ管名であればどの球であっても一定のバイアスを与えてやればプレート電流はある程度の範囲内に収まってくれるのとは大違いです。
再びバイアス回路
というわけで、さきほどの増幅回路のバイアスの与え方についてもういちど考え直してみることにします。バイアス電流を取り出すポイントをB+からコレクタに変更してみます。
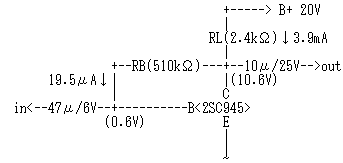 少し安定度の増した簡易バイアス回路
少し安定度の増した簡易バイアス回路
こうすることで、コレクタからベースに強度の直流帰還がかかります(真空管回路でいうP-G帰還と同じ原理です)。hFEが大きくなると、コレクタ電流が増加する。コレクタ電流が増加すると、コレクタ電圧が下がる。コレクタ電圧が下がると、コレクタ・ベース間電圧が下がって510kΩにかかる電圧も下がり、ベース電流が減少する。ベース電流が減少すれば、コレクタ電流も減少する・・・というフィードバックがかかって、動作がより安定方向に向くわけです。このバイアス方法は、少ない部品でそれなりの効果が得られるため、安価なオーディオ回路に多用されました。しかし、この方法にも限界があります。しかも、コレクタからベースには交流的にみても帰還がかかってしまうため、最近ではあまり使われることはありません。
トランジスタを1段増幅として思い通りの動作、安定した動作をさせるには、もうすこし手の込んだバイアス方法が必要です。もっともベーシックな方法は、エミッタ側に抵抗を挿入してエミッタ電流(すなわちコレクタ電流+ベース電流)を拘束する、というものです。
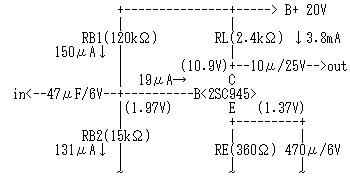 充分な安定度が得られるバイアス回路
充分な安定度が得られるバイアス回路
まず、2本の抵抗(RB1とRB2)とで電源電圧を分流し、比較的安定した基準電圧を作り出します。ここにベースをくくりつけておいてベース電流を取り出すわけですが、エミッタ側にも抵抗(RE)を追加します。ベース・エミッタ間電圧が0.6Vほぼ一定であることを利用して、エミッタ抵抗を使ってコレクタ電流を強制的にコントロールするわけです。そのとき、RB1、RB2にはベース電流よりも十分に大きな電流を流してやり、hFEやベース電流の変動によって、ベースに与えられる基準電圧が影響を受けにくくします。
このとき、エミッタに抵抗がはいりますから、増幅回路としてみた時に強度の電流帰還がかかってしまい、利得の減少を招きます。これを回避するために、エミッタ抵抗(RE)にバイパス・コンデンサ(470μF)を抱かせます。
エミッタ・フォロワ
真空管回路には、カソード・フォロワというのがあります。利得がおおよそ「1」しかなく、出力インピーダンスがとても低いあの回路です。トランジスタにもこれとそっくりの回路があり、エミッタ・フォロワといいます。
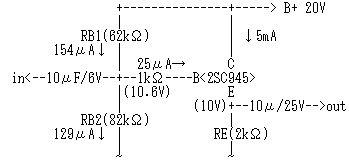 エミッタ・フォロワの基本回路
エミッタ・フォロワの基本回路
考え方は、真空管もトランジスタもほとんど同じです。違うのは、真空管ではグリッド電圧よりもカソード電圧の方が、グリッド・バイアス分だけ高くなりますが、トランジスタではベース電圧よりもエミッタ電圧の方が約0.6V低くなるということ。それから、真空管のグリッドには基本的に電流は流れ込まないと考えてよいですが、トランジスタのベースにはベース電流が流れ込むということです。このことを考えてRB1とRB2を決めてやります。
なお、ベース側に入力と直列に1kΩの抵抗が挿入されています。これは、トランジスタ回路のお作法のようなもので、トランジスタ回路では、ベースからみた信号源インピーダンスが極端に低くなることを嫌います。常識的に考えると、信号源インピーダンスは低い方が良さそうに思えますが、トランジスタではちょっと事情が違うのです。たとえば、トランジスタの雑音指数は信号源インピーダンスがある一定値の時に最小になります。また、信号源インピーダンスがゼロに近くなってくると、トランジスタの動作が不安定になりやすくなります。
