トランジスタの名称とタイプ
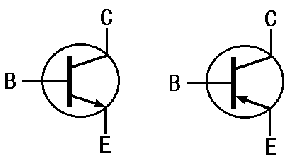 日本で製造・販売されているトランジスタの名称は4つに分類されます。「2SAなんとかかんとか」「2SBなんとかかんとか」「2SCなんとかかんとか」「2SDなんとかかんとか」の4つです。「2SC」と「2SD」は、回路図表上エミッタの矢印が外側を向きしますが(右図側左)、「2SA」と「2SB」は、回路図表上エミッタの矢印が内側を向きます(右図右側)。
日本で製造・販売されているトランジスタの名称は4つに分類されます。「2SAなんとかかんとか」「2SBなんとかかんとか」「2SCなんとかかんとか」「2SDなんとかかんとか」の4つです。「2SC」と「2SD」は、回路図表上エミッタの矢印が外側を向きしますが(右図側左)、「2SA」と「2SB」は、回路図表上エミッタの矢印が内側を向きます(右図右側)。「2SA,B系列」と「2SC,D系列」とではどこが違うのかというと、電流の流れる方向が全く反対なのです。真空管でいえば、プレートにプラスの電圧を与えてプレートからカソードに向かって電流が流れる・・・「2SC,D系列」・・・というところが、「2SA,B系列」では、プレートにマイナスの電圧を与えてカソードからプレートに向かって電流が流れる・・・変な話だ・・・ということになります。
「2SCなんとかかんとか」で組んだ回路を、回路図そのままにしてトランジスタだけ「2SAなんとかかんとか」に入れ替えたならば、電源電圧をプラスからマイナスにひっくりかえすだけで、その回路は同じように動作してしまうのです(電解コンデンサの極性も反対になります)。
接合の構造からこれらをそれぞれ、「2SC」と「2SD」を「NPN型」、「2SA」と「2SB」を「PNP型」と呼びますが、話がいよいよ長く難しくなってしまうのでこれ以上の構造に関する説明は省略します。
ちなみに、2SC945と正反対の特性を持った2SA733というトランジスタがあります。NPNとPNPのペアというわけです。これを「コンプリメンタリ・ペア(略してコンプリ・ペア)」といいます。ただし、コンプリ・ペアの電気的特性は厳密には正反対ではなく、ベース・エミッタ間電圧はPNP型の方が若干低めであるとか、hFEのコレクタ電流依存性はPNP型の方がちいさい、といった違いがありますので、あくまで反対の特性を持った似た者と考えなければなりません。
さて、「2SA」と「2SB」とはどこが違うのかというと、主なる用途で区別されています。トランジスタが登場した頃、その用途はほとんどラジオが中心でした。初期のトランジスタはコレクタ-エミッタ間の容量が大きく、高周波回路に使うためには特別に容量の小さなものが必要でした。こういう用途を意識して作られたトランジスタには「2SA」が冠せられ、それ以外の低周波用トランジスタには「2SB」が冠せられたのです。
「2SA」と「2SC」が高周波用、「2SB」と「2SD」が低周波用、ということになっています。しかし、最近のトランジスタは、かつてのものとは比較にならないくらい高周波性能が向上しており、オーディオ帯域でみる限り、この区別はあまり意味がなくなってきていることも事実です。これをまとめたのが下表です。
| 高周波用 | 低周波用 | 電流の流れる方向 | ベース・エミッタ間電圧(VBE) | |
|---|---|---|---|---|
| PNP型 | 2SA | 2SB | コレクタ←エミッタ、ベース←エミッタ | 約0.55V〜0.58V |
| NPN型 | 2SC | 2SD | コレクタ→エミッタ、ベース→エミッタ | 約0.6V |
ゲルマニウムとシリコン
最初に実用化されたトランジスタはゲルマニウムを使っていました。ゲルマニウム・トランジスタ、ゲルマニウム・ダイオードなどと呼ばれています。ゲルマニウム・トランジスタは、耐圧を高くするのが難しく、またベース・エミッタ間電圧がコレクタ電流や温度変化の影響を受けやすく、安定した動作をさせるのがちょっと難しいところがあります。シリコンを使ったトランジスタが登場するに至って、高温、高耐圧、高hFE、低雑音、大電力そして高周波特性のすぐれたトランジスタがたくさん供給されるようになりました。
設計上の大きな違いはベース・エミッタ間電圧にあります。シリコン・トランジスタが約0.6Vで比較的安定している(それでもコレクタ電流値や温度の影響は確実に受けますが)のに対して、ゲルマニウム・トランジスタでは約0.2Vからはじまってコレクタ電流の増加とともに0.3V、0.4Vとどんどん高くなってゆき、温度が上昇すると今度はどんどん低くなってゆきます。ここでは詳しく説明しませんが、ゲルマニウム・トランジスタのこういった性質は、温度上昇にともなうトランジスタの熱暴走と破壊の原因になるのです。
| 接合部温度 | ベース・エミッタ間電圧(VBE) | VBE(温度依存性) | |
|---|---|---|---|
| シリコン | 125℃〜150℃ | 約0.6V〜 | ほぼ一定していて1℃上昇するごとに2mV減少 |
| ゲルマニウム | 85℃〜105℃ | 約0.2V〜 | 温度上昇にとても敏感 |
注:ベース・エミッタ間電圧(VBE)は、コレクタ電流が増加すると徐々に高くなってゆくという性質もあります。シリコン・パワートランジスタの場合、少電流では0.6Vでも、数アンペア流すと1V以上になってゆきます。また、微少電流では0.5Vくらいまで低下します。
トランジスタの定格
真空管の主なる定格に、「最大プレート電圧」「最大プレート電流」「最大プレート損失」そして3定数「μ」「gm」「rp」等がありました。トランジスタの場合は、「コレクタ・エミッタ間電圧」「コレクタ・ベース間電圧」「コレクタ損失」「ジャンクション温度」「コレクタ電流」そして「hFE」「ノイズフィギュア」等があり、真空管に似ているようでずいぶん違っています。ここでは、トランジスタの主な定格について簡単に説明したいと思います。
| 「コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)」 「コレクタ・ベース間電圧(VCB)」 |
真空管と比べると、トランジスタは耐圧に関してクリティカルです。真空管であれば、短時間であれば耐圧オーバーは2倍まで許容されています。しかし、トランジスタの場合は一瞬たりとも許容耐圧を越えることは即破壊につながります。いかなる場合も許容される耐圧を越えてはなりません。 |
| 「コレクタ損失(PC)」 | 真空管、特に出力管では、プレート損失一杯まで使うのが普通でした。トランジスタは温度に対しても非常にデリケートなところがあり、規格表の表記は、周囲の気温25℃で理想的な放熱状態の場合の許容値で表記されています。日本の気温は35℃を越えることはよくありますし、トランジスタの周囲温度が常に25℃を維持できるわけではありませんから、食わせることができるコレクタ損失は定格値よりもずっとちいさな値になります。 トランジスタの規格表では、コレクタ損失には2種類の表現があります。(1)トランジスタをそのまま裸の状態で周囲温度25℃の状態において動作させた時に食わせることができるコレクタ損失値、そして(2)トランジスタに無限大の放熱板を取りつけて強制冷却し、ケース温度25℃の状態において動作させた時に食わせることができるコレクタ損失値です。前者(1)は小型で放熱板を取りつける構造になっていないトランジスタに多くみられ、後者(2)は中大型で放熱板を取りつけて使用する構造になっているトランジスタが多くなっています。 どれくらいの放熱板を取りつければ何Wまで大丈夫かは、ちゃんと計算する方法がありますが、ここでその説明をはじめてしまうと非常に長くなってしまうので、しかるべき文献に預けることにします。 |
| 「ジャンクション(接合部)温度(Tj)」 | 「Tj」と書いてジャンクション(接合部)温度といいます。半導体には接合部というポイントがあって、この部分で熱が発生します。発生した熱はトランジスタ本体を熱伝導して外に逃げてゆきます。 そして、トランジスタごとに接合部に許容される最高温度が決められており、これをジャンクション温度あるいは接合部温度といいます。ジャンクション温度は、上記コレクタ損失の算出の時に使用します。 |
| 「コレクタ電流(IC)」 | コレクタ電流を増加してゆくとhFEは徐々に増加してゆき、ある一定のコレクタ電流値を越えるとhFEはどんどん減少してゆき、やがて急激な減少をはじめます。トランジスタに許容されるコレクタ電流の最大値は、破壊に至る許容電流値よりもむしろもうこれ以上コレクタ電流を増やしてゆくとhFEが低下してしまってトランジスタとして動作できなくなる、というポイントをめやすに決定されることが多いです。そして、コレクタ電流の最大値が3Aのパワートランジスタの場合、3Aいっぱいまで動作させるとhFEが低くなりすぎていると解釈した方がよいでしょう。3Aまで安定した動作をさせたかったら5A以上の定格を持ったトランジスタを選定することをおすすめします。 |
| 「hFE」 | 直流電流増幅率といってベース電流(IB)に対するコレクタ電流(IC)の増幅率のことです(前章「1.トランジスタの基礎知識その1 (動作の基本) 」で説明しました)。規格表をみると、コレクタ・エミッタ間電圧(VBE)とコレクタ電流(IB)が併記されていますが、それはhFEがコレクタ電流によって変化する性質を持っているからです。 トランジスタが登場した頃は、hFEは80もあればずいぶん高い方でした。やがてhFEが400を越えるものも登場するようになり、トランジスタ回路はずいぶん設計しやすくなってきました。一般に、高圧に耐えるトランジスタのhFEは非常に低く(10程度というのはザラ)、大電力を扱えるトランジスタもそんなに高くなく(50〜200くらいが多い)、小電力で特に低雑音用は高め(200〜800)になっています。 NPNトランジスタでは、コレクタ電流値が小さくなるにつれて、hFEも徐々に低下してゆき、微少電流領域ではかなりの低下をみます。PNPトランジスタでは一般に、この低下の具合が少なく、微少電流領域での低下がNPN型ほど顕著ではありません。 |
| 「ノイズフィギュア(NF)」 | 規格表上で「NF」と略されているのがこのノイズフィギュアのことで、トランジスタ自身で発生する雑音の指数です。低雑音目的のトランジスタに表記されていることが多く、NF=3dBとかNF=1dBといった表現がなされます。 トランジスタで発生するノイズの量は、(1)コレクタ電流、(2)信号源インピーダンス、の2つの組み合わせで決定されます。コレクタ電流は、多くても少なくてもノイズフィギュアは悪化し、また、信号源インピーダンスも大きくても小さくてもノイズフィギュアは悪化します。そのため、プリアンプのPHONO入力回路等では、初段のベース入力側にわざわざ抵抗を直列に割り込ませたりします。だいたいのところ、コレクタ電流数十μA、信号源インピーダンス数kΩあたりでノイズは最小になります。 |
hFEの測定法
hFEは、直流電流増幅率といってベース電流(IB)に対するコレクタ電流(IC)の増幅率のことでした。ですから、簡単な回路を組んで、動作中のベース電流(IB)とコレクタ電流(IC)を測定し、その比を求めればhFEを求めることができます。着目すべきはhFEの性質で、電圧依存性が非常に低いために、コレクタ〜エミッタ間電圧は実際の動作条件よりもずっと低い値でもかまわないということです。トランジスタ規格表を見ても、ほとんどのデータが3Vとか10Vといった電圧で測定しています。そこで、簡易型の測定回路では、単1または単2乾電池を2本使い、コレクタ〜エミッタ間電圧は約3Vで測定することにします。
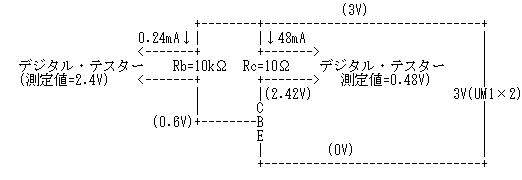 右図が測定回路です。トランジスタのエミッタ〜ベース間電圧は、コレクタ電流値にもよりますが、0.5V〜1Vくらい、2SD799のように内部的にダーリントン接続になったトランジスタでは0.9V〜1.4Vくらいの範囲になります。右図では、ベース抵抗(Rb)が10kΩで、その両端電圧が2.4Vですから、ベース電流は0.24mAになります。その時、10Ωのコレクタ抵抗(Rc)の両端電圧が0.48Vであったならば、コレクタ電流は48mAですから、hFEは、
右図が測定回路です。トランジスタのエミッタ〜ベース間電圧は、コレクタ電流値にもよりますが、0.5V〜1Vくらい、2SD799のように内部的にダーリントン接続になったトランジスタでは0.9V〜1.4Vくらいの範囲になります。右図では、ベース抵抗(Rb)が10kΩで、その両端電圧が2.4Vですから、ベース電流は0.24mAになります。その時、10Ωのコレクタ抵抗(Rc)の両端電圧が0.48Vであったならば、コレクタ電流は48mAですから、hFEは、
hFE = 48mA ÷ 0.24mA = 200
となります。ベース電流は、ベース抵抗(Rb)の値でほとんど決定されてしまいますから、Rbをいろいろな値の抵抗器に置き換えることによって、さまざまな条件を作り出すことができます。
注意しなければならない点が2つほどあります。1つめは、コレクタ〜エミッタ間電圧は、ある一定値以下になるとトランジスタが正常に動作しなくなること・・・これを、コレクタ〜エミッタ間飽和電圧という・・・です。コレクタ〜エミッタ間電圧は、1V以上、できれば2V以上確保してください。2つめは、最大コレクタ損失およびコレクタ電流値は、トランジスタの最大定格を越えてはならない、というごくあたりまえの約束です。
同じトランジスタでも、コレクタ電流が、1mAの時、10mAの時、100mAの時では、hFEの値は驚くほど変動します。また、同じ名前のトランジスタでも、hFEの値は個々に相当なばらつきがります。そのあたりの感覚をつかむために、いるいろな実験をしてみたらいいと思います。そうすることによって、トランジスタの性質をより深く理解し、自分のものにできるでしょう。
