コンデンサの特性を表わす数値
容量・許容差・温度係数
コンデンサの容量は「F(ファラッド)」とその1/1000000の「μF(マイクロ・ファラッド)」、さらに1/1000000の「pF(ピコ・ファラッド)」で表わされます。容量の許容差は、一般に5%〜20%くらいがほとんどですが、ポリスチレン、マイカ、ガラス、温度補償用セラミックなどでは1%よりも高い精度のものが作られています。ただ、広帯域であらゆる周波数で容量値が正しく機能するわけではなく、またアルミ電解コンデンサのように測定する周波数によって容量が変わってしまうものもあります。容量は温度によって変化し、この度合いを表したのが温度係数です。温度係数はコンデンサの種類によってまちまちです。積層セラミック・コンデンサの中には温度によって容量が著しく変化するものも作られています。
定格電圧・絶縁抵抗・洩れ電流
WV(Work Volt)またはV(Volt)で表わします。使用上は定格電圧を越えないことが基本ですが、アルミ電解コンデンサのように、短時間であれば許されるサージ電圧が規定されているものもあります。ちなみに、アルミ電解コンデンサのサージ電圧(US)は、定格電圧(UR)を超えた電圧ですが、JISでは、次の内容になっています。
UR ≦200Vのとき、 US = UR×1.25倍
UR >200Vのとき、 US = UR+50V
の電圧を規定の温度で、30秒間印加,5分30秒間放置を1000回繰り返すことを保証しています。
絶縁抵抗は、通常MΩで表示されますが、アルミ電解コンデンサのように、洩れ電流値が印加された電圧に比例しない場合は、漏れ電流値で表示します。アルミ電解コンデンサは、そもそも、構造的に漏れ電流が発生するようになっており、すくなからず漏れ電流が生じるということを前提で設計しなければなりません。
フィルムコンデンサは、きわめて高い絶縁抵抗を持つことが知られていますが、その実態は案外脆いところがあります。十年以上前に組み上げたメインアンプの出力管のグリッド電位をあたってみると、0Vのはずのグリッドに数Vの電圧が観測されることがありますが、これは、経年変化によるフィルム・コンデンサの絶縁低下によるものです。フィルム・コンデンサの中でも例外的に絶縁性能が優れているのが、誘電体にポリプロピレンを使用したものです。ポリプロピレン・コンデンサは、ややかさばることと、かなり高価だという欠点がありますが、後述するように伝達特性も群を抜いて優れています。
ESR(等価直列抵抗)
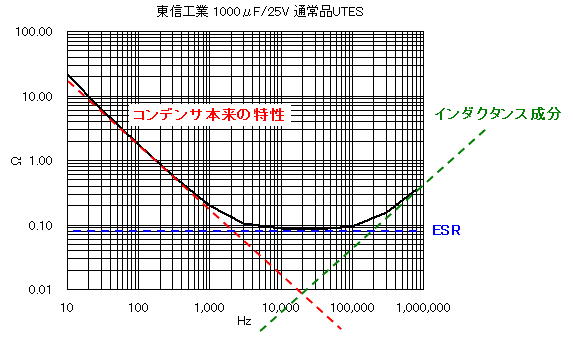 実際のコンデンサは、理想コンデンサに抵抗とインダクタを直列にしたような特性を持っています。この、理想コンデンサと直列にはいっている抵抗成分のことを、ESR(等価直列抵抗)といいます。
実際のコンデンサは、理想コンデンサに抵抗とインダクタを直列にしたような特性を持っています。この、理想コンデンサと直列にはいっている抵抗成分のことを、ESR(等価直列抵抗)といいます。右図で、右下がりの直線部分はコンデンサ本来のインピーダンス特性で、周波数が高くなるほどにインピーダンス値が小さくなってゆきます。ところが、周波数が高くなるにつれて横這いになり、コンデンサによって0.02Ω〜1Ωくらいで底を打ちます。この底を打った値がESRです。さらに高い周波数ではインピーダンスは上昇をはじめます。コンデンサの構造上コイル成分が存在するからです。
ESR値が大きいコンデンサに大きな交流電流を流すと、その抵抗分だけ発熱します。これが問題になるのは、電源回路の整流後のところに入れられたリプル・フィルタ用コンデンサです。このコンデンサには、大きなリプル電流が流れるため、電源のリプル・フィルタ用コンデンサのなかで最も発熱しますが、このリプル電流が定格値を越えると、コンデンサがパンクしたり寿命が極端に短くなったりします。
アルミ電解コンデンサには、特に「低ESR」と称するものがあります。低ESRの効果が発揮されるのはごく限られた帯域だけです。右図でいうと、低ESRの性能が発揮されるのは40kHz〜100kHzの範囲です。なお、アルミ電解コンデンサの低ESRタイプと通常タイプと差はあまり大きくなく、低ESRでもせいぜい1/2どまりです。ESRが圧倒的に低いのはOSコンなどの有機半導体系のコンデンサです。
具体的なデータはこちらにありますので参考にしてください。
損失角の正接(tanδ)
工事中
コンデンサの種類と特徴
参考文献:http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2005/04/p211-212.pdfフィルム・コンデンサ
一般にフィルム・コンデンサと呼ばれるものは、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレンなどのプラスチックを誘電体に使います。おしなべて、絶縁の高さと誘電損失の低さが特徴ですが、それでも誘電体によってかなりの差があります。何度も言うようですが、フィルム・コンデンサといえども、条件によっては決して高絶縁とはいえないということです。1000MΩの絶縁があったとしても、200Vのところから100kΩの抵抗とで分流した場合、100kΩの抵抗の両端には0.02Vの電圧が生じます。これが12AX7のグリッドだったら、プレート電圧にはその60〜70倍の電圧(1.2〜1.4V)となって現れることになります。そして、このような高絶縁はいつまでも持たずに徐々に劣化してゆきます。以下に、誘電体ごとの違いをまとめてみました。
(1)ポリスチレン・コンデンサ
いわゆるスチコンと呼ばれているコンデンサです。誘電体にポリスチレンが使われており、独特の形状(円筒形の透明なプラスチック)であるため、外見で簡単に判断できます。絶縁抵抗が高く、誘電損失もきわめて少ないのでオーディオ用として良く使われます。精度の高いものが作れるため、イコライザ素子によく使われました。耐圧があまり高くないものが多いので注意がいります。ただ、コストが高いのと小型化できないために工業用としてのニーズがなく、事実上の製造中止となりました。
(2)ポリプロピレン・フィルム・コンデンサ
フィルムコンデンサの仲間の中では、誘電正接(tanδ)が圧倒的に優れています・・・ポリエステルの1/5〜1/25。絶縁抵抗も、ポリエステルに比べて一桁のオーダーで高くなっています。欠点としては、ややかさばることと、やや高価なことでしょう。しかし、フィルム・コンデンサも経年変化によって絶縁性能は思いのほか劣化しますし、これが段間の結合コンデンサだと、次段のグリッドがプラスの電位になっていた、などということも良く起こりますから、このポリプロピレン・フィルム・コンデンサの価値は高いと思います。ただし、ポリプロピレン・フィルムは耐熱性があまり高くないので、周囲温度が60〜70℃以上になるような場合は、耐圧を割り引いて使わなければなりません。このコンデンサは物理特性は非常に優れているのですが、何故か音に独特の色気のようなものがつく傾向があり、オーディオ用としての評価は分かれます。
(3)ポリエステル(マイラ)・フィルム・コンデンサ
最も一般的なフィルム・コンデンサで、マイラ・コンデンサとも呼ばれています。安価に作れるのが特徴で、性能的には耐熱性をのぞくあらゆる面でポリスチレンやポリプロピレンより劣りますが、それでもアルミ電解コンデンサに比べれば圧倒的に優れています。とりたてて特徴のないコンデンサなのですが、その特徴のなさのおかげでナチュラルな音が得られやすいというメリットがありますので、私は好んで使います。
(積層)セラミック・コンデンサ
セラミック・コンデンサの歴史は古く、フィルム・コンデンサがなくオイル・コンデンサの全盛期からラジオなどでごく普通に使われてきました。円盤型の廉価なコンデンサは今でも売られています。セラミック系のコンデンサの特徴は、小容量のものに適するということと(最近はかなり大容量のものも出てきている)、とにかく安いということでしょうか。セラミックには、圧力をかけると発電し電圧をかけると振動するという面白い特性があります。また、温度変化によって容量が著しく変化します(しないものもある)。この性質を逆に利用して、温度変化と容量変化が直線的な相関を持つものを作って、温度補償として売られているくらいです。さらに、印加した電圧によって容量が変化します(DCバイアス特性という)。こうしたさまざまな特性変化は、製造時の配合の具合によってコントロールされています。
そのため、セラミック系のコンデンサを不用意にオーディオ回路で使用すると、信号電圧がかかることで容量が変化してしまって音が変調されてしまうなど、さまざまな問題が生じます。もちろん、ごく少数ですが印加した電圧によって容量が変化しないタイプもあります。購入においては型番とメーカーのテクニカル・ドキュメントを突き合せてチェックするなど慎重を期する必要があります。ジャンク品ではもはや正体はわかりません。
マイカ・コンデンサ
誘電体にマイカ(雲母)を用いたコンデンサで、キャラメルのような外観で知られています。精度が出しやすいのと、誘電損失も比較的低いのですが、高価なのが欠点です。かつては、高周波特性といえばマイカ・コンデンサが良いと言われてきましたが、これはフィルム・コンデンサが普及していなかった時代のことで、今日では非常に優れたフィルム・コンデンサが登場したため、今やマイカ・コンデンサの出番はほとんどなくなってしまいました。殊更にお金を積んでビンテージものの高価なマイカ・コンデンサを求めることもないでしょう。ただ、400V以上の耐圧ものもが容易に作れるので、高圧がかかるオーディオ回路では非常にありがたいコンデンサでもあります。
オイル・コンデンサ
1970年頃は、真空管回路のカップリング用といえばもっぱらこれでした。・・・。
アルミ電解コンデンサ
アルミ電解コンデンサは、1908年、GE(General Electric)社によって開発されました。このアルミ電解コンデンサについて理解しておかなければならないポイントはたくさんあります。1つめは、容量において他のコンデンサと大きく異なる点があります。それは、測定条件によって容量値がどんどん変化するということです。アルミ電解コンデンサの容量値は、20℃、120Hz(または1kHz)の交流で測定されますが、容量値は、高温になると大きくなり(20℃→50℃の変化で105%〜110%になる)、低温になると小さくなります(20℃→0℃の変化で90%〜97%になる)。また、周波数が高くなると小さくなります(120Hz→10kHzの変化で60%〜70%になる)。つまり、全く一定ではないということです。従って、メーカーのテクニカル・ドキュメントには「時定数回路への使用は不可」と書かれています。
2つめは、封入されている電解液は、時間とともに封口部から徐々に外部に拡散してしまうということです。このスピードは、温度が高いほど加速されます。ですから、電解コンデンサの劣化が進行するにつれて、重さも軽くなってゆきます。寿命は有限であり、使用条件によってはかなり短期間で劣化します。アルミ電解コンデンサの温度管理がうるさくいわれるのは、こういう理由で劣化が急激に早まるからです。
3つめは、宿命的に、常に洩れ電流が存在するということです。誘電体である酸化皮膜は、漏れ電流の存在によって常時修復され続けています。従って、高い絶縁性能が必要な個所では使うことができません。アルミ電解コンデンサを使わないで長期間放置しておいてから使用すると、漏れ電流が正常時の10〜100倍くらい増加します。誘電体の皮膜の修復のためにより多くの漏れ電流が流れるからです。
上記の3つの問題だけでなく、周波数特性が悪く、誘電損失が大きいという欠点は、最近は相当に改善されてきています。従って、古くに製造されたアルミ電解コンデンサは、最近製造されたものに比べるとかなり劣っており、しかも、古くに製造されたものは時間が経っている分さらに劣化が進行していると考えなければなりません。アルミ電解コンデンサは「生鮮部品」ですから、古くなったものを再利用するのは賢明ではありません。
このように電気的特性はあまり良くないのですが、そのことを極端に解釈して「アルミ電解コンデンサだけだと高域が出ない」と思い込んでいる人が多いように思います。アルミ電解コンデンサは巷で言われているほど高周波特性が悪いわけではありません。ましてや可聴帯域でレスポンスが低下するなどという馬鹿なことは起こりません。アルミ電解コンデンサにフィルム・コンデンサを抱かせている回路を見かけますが、フィルムコンデンサでも、容量が大きいものでは高周波特性がアルミ電解コンデンサよりも劣るものはいくらでもあります。
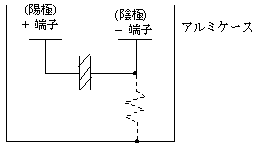 アルミ電解コンデンサは、10℃以下の低温では、等価直列抵抗(ESR)が大きくなるなど、極端に性能が劣化しますので使用環境については注意が必要です。冬場、冷え切ったアンプの電源を入れた直後では、リプルが十分に除去できずにハムが出たり、低域性能が悪いためにいつもどりの音がでなかったりします。
アルミ電解コンデンサは、10℃以下の低温では、等価直列抵抗(ESR)が大きくなるなど、極端に性能が劣化しますので使用環境については注意が必要です。冬場、冷え切ったアンプの電源を入れた直後では、リプルが十分に除去できずにハムが出たり、低域性能が悪いためにいつもどりの音がでなかったりします。
ところで、アルミ電解コンデンサの外側の金属パッケージはどこに接続されているのでしょう。チューブラー型の場合は、じかにマイナス側に接続されている様子を目で確かめることができますが、縦形の場合は、コンデンサのアルミケースと陰極端子間は、ケース内側の自然酸化皮膜と電解液(又は電解質)の不安定な抵抗分で接続されています(右図)。そして、樹脂の被覆チューブは絶縁目的のものではありませんから、他の部品等に接触しないような配慮がいります。
タンタル電解コンデンサ
タンタル電解コンデンサは、1953年、ウェスターンエレクトリック社とスプラーグ社によって開発されました。アルミ電解コンデンサと比較して、等価直列抵抗(ESR)が低く、漏れ電流特性、周波数特性、温度特性が優れていて、しかもドライアップがありません。当初は定格内で使っていてもショート事故を起こすという問題がありましたが、使用するタンタルに純度の高いものを使うなど工夫して、そういう事故はかなり減りました。しかし、逆電圧には非常に弱く、急激な充放電でも起こるショート事故が根本的に回避されたわけではありません。タンタル電解コンデンサの故障モードは90%が「ショート」です。万一、ショートが発生しても大事に至らないような設計が必須です。タンタル電解コンデンサには、固体タンタルと湿式タンタルの2種類があります。湿式タンタルは、固体タンタルよりもさらに洩れ電流が小さいという特徴がありますが、一方で、逆電圧には極端に弱く、アルミ電解コンデンサが、定格電圧の10%程度の逆電圧に耐えるのに対して、湿式タンタルでは、一瞬たりとも逆電圧をかけられません。逆電圧がかかると、容易にショート事故を起こします。
アルシコン
タンタル電解コンデンサの弱点を解決しようとして、佐賀三洋工業によって開発・商品化された(1970年)のが、アルシコンです。タンタル並みの性能を持ちながら、逆耐電圧や急激な充放電に強いという特徴があるのですが、6.3Vでは10μF、25Vでは1μFまでの容量しか商品化できませんでした。高校生の頃、6.2μF/6.3Vくらいのものを使った記憶があります。
OS(Organic Semiconductor=有機半導体)コン
アルミ電解コンデンサとタンタル電解コンデンサの両方の欠点を解決したのが、1982年、佐賀三洋工業によって開発されたOSコンです。OSコンは、その構造上、電解質が固体であるのと封入口がエポキシ樹脂で固められているため、電解コンデンサのようなドライアップがなくなり、高温にも耐え、寿命が著しく改善されています。低温特性、周波数特性が良く、誘電損失も非常に少なくなっています。当初は、その周波数特性の良さからデジタル回路やビデオ等の映像増幅回路の高性能化、小型化で脚光を浴びましたが、やがてオーディオ用としても評価されるようになりました。リード線にCP線(錫メッキ鋼線)を使ったスイッチング回路用とOFC(無酸素銅線)を使うなど工夫をこらしたオーディオ用(SGシリーズ)とが区別されています。
オーディオに向くという点では、OSコンの防振構造も大きな特徴です。コンデンサは、2つの電極間に働くクーロン力によって多かれ少なかれ振動します。交流信号を印加したフィルム・コンデンサが鳴くという現象はよく知られていますし、アルミ電解コンデンサも、聴診器を当てると箔の振動する音が聞こえますが、OSコンはそれがありません。
OSコンで注意しなければならないのは、固体電解質を使っているという宿命として、アルミ電解コンデンサと比較して酸化皮膜の修復能力が劣るという点です。皮膜のダメージが修復されないため、落下や圧迫等の衝撃を与えないようにしなければなりません。機械的にデリケートなのです。半田づけ時の加熱と冷却による皮膜の収縮は、酸化皮膜に微細なダメージを与えます。これによって一時的に性能が変化することがあるので、半田づけ後は、長時間通電エージングが必要な場合があります。
OSコンとアルミ電解コンデンサとの違いは、ESRの低さの違いに尽きると言っていいでしょう。手元にあるさまざまなコンデンサのESRを実測したことがありますが、100μF以下ではアルミ電解コンデンサのESRは0.5Ω〜1Ωくらいあるのに対して、OSコンは0.1Ω〜0.2Ωと圧倒的な低さでした。しかし、リードインダクタンスの影響による高周波特性の上限はOSコンもアルミ電解コンデンサも同じです。OSコンがアルミ電解コンデンサよりも高い周波数まで使えるというわけではありませんが、そこのところを勘違いされている方が多いように思います。
超大容量コンデンサ(スーパーキャパシタ)
非常にコンパクトなのに100000μF〜10000000μF(すなわち0.1F〜10F)という大容量のコンデンサがあります。このコンデンサは、容量は大きいですが、等価直列抵抗(ESR)が数Ω〜数十Ωときわめて高いため、電源のリプルフィルタやデカップリングには向きません。もっぱらコンピュータ等のバックアップ用途です。また、漏れ電流が1mA前後と多いため注意がいります。
コード表示の見方
コンデンサの表示は、「0.22μF 630V」という風にそのものずばり表示されているものと、「2G474J」といったコード表示のものがあります。コード表示は一見わかりずらく、購入した時にしっかり覚えておかないと後になってこれは何μFだったかな、とわからなくなってしまいますね。JISにおいて以下のように定められていますので、慣れてしまえば抵抗のカラーコード同様なんでもありません。「2G474J」のうち、頭の2桁「2G」が耐圧表示、続く3桁「474」が容量表示、最後の1桁「J」が精度表示です。それぞれの表示コードの体系を以下にまとめてみました。これは「耐圧400V、容量0.47μF、容量誤差10%」のコンデンサであったわけです。
耐圧:
「1E」ならば25V、「2J」ならば630Vの耐圧です。
| A | C | P | D | E | F | V | G | W | H | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | 3.15V | 3.5V | 4V | 5V | 5V | 6.3V | 8V |
| 1 | 10V | 16V | 18V | 20V | 25V | 31.5V | 35V | 40V | 45V | 50V | 63V | 80V |
| 2 | 100V | 160V | 180V | 200V | 250V | 315V | 350V | 400V | 450V | 500V | 630V | 800V |
容量:
上2桁が「10」「33」「22」「47」「68」の場合を表にしてみました。「101」ならば100pF、「473」ならば0.047μFの容量です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10pF | 100pF | 1000pF (0.001μF) | 10000pF (0.01μF) | 100000pF (0.1μF) | 1000000pF (1μF) |
| 22 | 22pF | 220pF | 2200pF (0.0022μF) | 22000pF (0.022μF) | 220000pF (0.22μF) | 2200000pF (2.2μF) |
| 33 | 33pF | 330pF | 3300pF (0.0033μF) | 33000pF (0.033μF) | 330000pF (0.33μF) | 3300000pF (3.3μF) |
| 47 | 47pF | 470pF | 4700pF (0.0047μF) | 47000pF (0.047μF) | 470000pF (0.47μF) | 4700000pF (4.7μF) |
| 68 | 68pF | 680pF | 6800pF (0.0068μF) | 68000pF (0.068μF) | 680000pF (0.68μF) | 6800000pF (6.8μF) |
なお、容量表記にはもうひとの方法があって、整数値はそのまま、小数点を「R」で表わすことがあります。最終桁は、乗数です。3数字の場合は、E3、E6、E12、E24に適用されます。下表の例を参照してください。
| R47 | 0.47 |
| 6R8 | 6.8 |
| 100 | 10 |
| 101 | 100 |
| 102 | 1000 |
許容差:
許容差は、抵抗器と同じコード体系です。「J級」といえば、コンデンサも抵抗も±10%の精度になります。
| B級 | 許容差±0.1% |
|---|---|
| C級 | 許容差±0.25% |
| D級 | 許容差±0.5% |
| F級 | 許容差±1% |
| G級 | 許容差±2% |
| J級 | 許容差±5% |
| K級 | 許容差±10% |
| M級 | 許容差±20% |
| N級 | 許容差±30% |
| P級 | 許容差+100% -0% |
| Q級 | 許容差+30% -10% |
| T級 | 許容差+50% -10% |
| U級 | 許容差+75% -10% |
| V級 | 許容差+250% -10% |
| W級 | 許容差+100% -10% |
| X級 | 許容差+40% -20% |
| Y級 | 許容差+150% -10% |
| Z級 | 許容差+80% -20% |
耐圧・容量が合わない場合
耐圧を高くするには
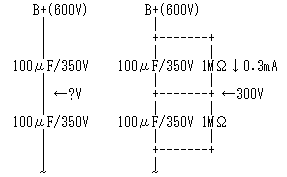 電解コンデンサの耐圧は、もっとも高いものでも500V程度です。しかも、450V以上の耐圧がある電解コンデンサの生産はどんどん縮小傾向にあります。801/VT62のような、600V以上の高い電源電圧で動作する球を使ったアンプでは、電源回路の平滑用コンデンサの調達で苦労します。このような場合、耐圧350V以上の2つの電解コンデンサを直列にすることで、600V以上の耐圧を得ることができます。
電解コンデンサの耐圧は、もっとも高いものでも500V程度です。しかも、450V以上の耐圧がある電解コンデンサの生産はどんどん縮小傾向にあります。801/VT62のような、600V以上の高い電源電圧で動作する球を使ったアンプでは、電源回路の平滑用コンデンサの調達で苦労します。このような場合、耐圧350V以上の2つの電解コンデンサを直列にすることで、600V以上の耐圧を得ることができます。右図を見てください。350Vの電解コンデンサ2個を直列にして、600Vに耐えるコンデンサ回路を作ろうとしています。2つのコンデンサの中間の電位は何Vになるのでしょうか。コンデンサは直流は流れないことになっていますが、それでも2つのコンデンサの中間の直流電位は決まるのでしょうか。
電解コンデンサは、構造的宿命として一定の漏れ電流が必ず流れます。しかし、2つのコンデンサの中間の電位が300Vになるかどうかは、なんとも言えないのです。何故なら、電解コンデンサの漏れ電流は不規則で、ばらつきがあって、経年変化もあって、全く一定ではありません。もし、上側のコンデンサの漏れ電流の方が多かったら、2つのコンデンサの中間の電位は300Vよりもずっと高くなります。
このような回路では、2つのコンデンサの中間の電位を300Vに安定させてやるために、高抵抗を抱かせて電解コンデンサの漏れ電流よりも大きな電流を流してやり、中間の電位をしっかりと固定させてやる必要があります。もちろん、直流電流が流れては困るような回路では、この手は使えません。
