
背面へ



このアンプは1996年(あるいはそれより以前)に作られた全段差動プッシュプルアンプの1号機です。私にとって全段差動がここからはじまりまった記念すべきアンプです。3極出力管が希少になり、市場価格がどんどんつり上がってしまいました。そんななか、テレビ球の中からオーディオ用として使えそうな球を見つけたのが6AH4GTです。少々バラツキのある球ですが、供給は豊富で・・・というか、人気がない・・・海外通販ならば1本$4.00程度で入手可能です。浅野勇氏著「魅惑の真空管アンプ下巻」の'50シングル・ステレオ/モノ兼用アンプのドライバとしても起用された6AH4GTは、6G-A4を小振りにしたような球です。シングル動作での試験でも、ミッドローが充実したサウンドを聴かせてくれ、迷わずプッシュプルで本機に採用しました。(そんな6AH4GTも、たぶん私のせいで徐々に品薄となり、値が上がってきてしまいました。そろそろ、身代わりを見つけなければ。2003.9.1)
初段からドライバ、出力段に至るまで、全段を差動プッシュプルにした本アンプは、もはや古典的な真空管アンプの面影はなく、ひたすら現代に通用するメインアンプ本来の特性を追求しています。
但し、設計当時はまだ全段差動アンプの挙動についてほとんど無知であったために、本アンプでは、今考えると無意味といえるほどの過剰投資をしてしまっています。B電源のリプル除去はここまでやる必要はありませんし、リプルフィルターを左右チャネルで分ける必要もないことが後になってわかりました。そこのところを十分に理解していただいた上で以下のレポートをお読みください。
Medium sized triode 6AH4GT is well known as TV use, however 6AH4GT has good sound for final stage of audio main amplifier. This is the first project for "All Stage Differential Amplifier" known in Japan as "Zen-Dan-Sado-PP-Amp", which is using Differential Amplifier Circuit for all stage including final.
本アンプは、初段から出力段に至るまで全段が差動回路で構成されています。各段がなぜ差動動作となったのかは、それぞれ別個の理由があり、ただやみくもにすべてを差動にしたわけではありません。いろいろな問題を解決してゆくうちに結果的にすべての増幅段が差動になってしまったのです。
プッシュプル・アンプの設計で最も悩ましい(いいかえると、考えるのが楽しい)問題は、位相反転をどのようにして行うかでしょう。対称性の高い位相反転を望むならばムラード型の位相反転回路がポピュラーです。ムラード型位相反転回路は差動回路そのものですが、これを差動回路と呼んだ記事は見たことがありません。この回路で対称性の高い位相反転を行わせたければ、共通カソード抵抗値を相当に高く設定する必要があります。現実のアンプでは高抵抗は無理なので、上下のプレート負荷抵抗の値を変えることで位相反転精度の悪さを補っています。こんなことをやっているので、もはや差動回路とは呼べないのかもしれません。抵抗ではなくここに定電流回路を挿入すれば申し分ありませんが、そういう構成の製作例は何故かあまりみかけません。真空管アンプに半導体を持ち込むのは抵抗があるのでしょう。では、初段はどうかというと、ムラード型では初段はシングル動作のままですからここで発生する2次歪みは打ち消されることなく出力に現れてきます。ドライバ(=位相反転)段の利得が低いと、ドライバ段の必要入力電圧、すなわち初段の出力電圧が高くなって初段で発生する2次歪みが相対的に大きくなってしまい、無視できなくなってきます。この問題は、出力管が感度の低い直熱3極管の場合や、位相反転にμの低い12AU7や5687等を使用した場合に顕著に現われます。実際、初段で発生する歪みが、出力段で発生する歪みよりも大きくなってしまうことすらあるのです。LUXのSQ38FDは、ドライバ段にμが高い6DT8(12AT7と同特性)を採用することで、ドライバ段で利得を稼ぎ、初段の負担を軽くして初段で生じる2次歪みの軽減を図っています。
この問題を解決するもう1つの方法は、初段でいきなり位相反転を行い、しかもドライバ段も差動のままにしておくということです。こうすることによって、初段がシングル動作ではなくなるので、初段で発生していた2次歪みはなくなります。また、プッシュプル・バランスも精密にとれるようになります。プッシュプル・バランスは、半導体や真空管の個々の特性のバラツキの影響は一切受けなくなり、各段のプレート(あるいはドレイン)負荷抵抗の精度だけで決定されるようになります。本機が初段・ドライバ段ともに差動動作となっているのはこのような理由からです。
ちなみに、差動回路を実現するためには、共通カソード(またはソース、またはエミッタ)抵抗を定電流回路化するのが望ましいです※。定電流回路としては、定電流ダイオード(CRD)を使う、トランジスタで組む、FETまたは5極管を使う等の方法が一般的です。回路電圧が低くて回路電流も少ないならば定電流ダイオード(CRD)で問題ありませんが、回路電流が多い場合はパワートランジスタを使って組むことになり、また回路電圧が高い場合は5極管の出番も考えられます。
※後になって、定電流性能はさほど重要ではなく抵抗器のようなやや不十分なものでも満足できる結果が得られることがわかってきました。当時は、ひたすら定電流性能を高めた方がいいのではないか、と思ったわけですがそれは思い込みだったようです。さて、本機のような構成では、初段だけでなくドライバ段も位相反転機能を営みます。なぜなら、ドライバ段の共通カソード側も定電流ダイオードによって定電流化されているからです。初段でプッシュプル信号のアンバランスが発生しても、ドライバ段できれいに補正されてしまいます。反対に、初段できれいな信号バランスが取れても、ドライバ段のプレート負荷抵抗値が揃っていないとドライバ段でバランスが狂います。もし、ドライバ段をプッシュプルとしながらも、共通カソード側を定電流回路にしないでコンデンサで接地したとします。このような場合には、プッシュプルというよりも2つのシングル増幅回路がそれぞれ勝手に増幅作用を営むのと変わりありませんので、もし2つのドライバ管の利得にバラツキがあった場合、出力段に送り込まれる信号のプッシュプル・バランスは狂ってしまいます。そういう意味でも、ドライバ段の差動化は重要な意味をもちます。
全段差動構成の増幅回路は、全段トランス結合のプッシュプル回路ときわめて良く似た特徴を持ちます。トランス結合のプッシュプル回路では、コモンモード信号が遮断されます(CMRR=Common Mode Rejection Ratioが高い)が、全段差動構成の増幅回路でも同じことが起こります。アースや電源ラインに信号が全く流れなくなるからです。実は、全段を差動にした最大の理由は、アースや電源ラインに一切信号を流したくなかったからなのです。差動構成の増幅回路は、トランスを使わない平衡増幅回路といってもいいでしょう。
アンプ部の回路は以下の通りです。
電源部の回路は以下の通りです。

入力信号は、初段2SK30Aの差動プッシュプルで受けています。反対側の2SK30Aのゲートは負帰還の入力となっており、負帰還量をドライバー1本で調節できるように100Ωの半固定抵抗器を入れてあります。当初の設計では、初段は12AU7を使って2段差動直結とするつもりでした。しかし、真空管を使っての差動直結は信頼性を欠きます。前段のプレート電圧に僅かなバラつきが生じても後段の動作は破綻します。初段が真空管ではなくFET(2SK30A)となったのは、半導体ならば真空管のような経年変化がほとんどないからです。一旦DCバランスを取ってしまえば長期にわたってその状態が維持されす。シャーシ(30cm×10cm×6cm)のスペースに全然余裕がないのと、「6G-A4シングルアンプその2」で2SK30Aを初段に採用しての成功も理由です。
本機では、無調整のまま差動プッシュプル動作で2段直結を実現するために、使用した2SK30Aはかなり厳密な選別を行っています(直流バランスの調整回路をつけるならばこんな厳密な選別はいりません)。Idssだけでなくgmも同時に揃うように30本の2SK30A(Yクラス)のなかから特性が近い4本を選んでいます。
右図が、初段2SK30A(Y)の動作条件です。共有ソース側の定電流ダイオードの設計値が2mAであるため、2SK30A1本あたりのドレイン電流は、自動的に半分の1mAに決まります。電源電圧24V、バイアスが約-0.5V、負荷抵抗が10kΩですから、23.5Vを起点とした10kΩのロードラインになります。
動作ポイント付近のgmは、-0.4Vと-0.6Vの特性曲線の間隔から求まります。グラフ上からおおよそのところを読み取ると「-0.4V〜-0.6V」で「1.16mA〜0.8mA」ですから、gm=0.36mA÷0.2V=1.8が求まります。初段の利得は、A=10kΩ×1.8÷2=9倍です。入力信号が上下の2SK30Aで2分されてみかけの利得が1/2になるため、1段あたりの利得を2で割っています。
ドレイン負荷抵抗値を大きくすれば、もっと高い利得と低い歪み率が得られますが、利得に比例して2SK30Aのバラつきの影響が出てしまいます。選別では、ドレイン電流を1mA流した時のバイアスが0.03V以下にすると、ドレイン電圧に現れるバラつきの影響を0.54V以下に抑えることができます。この差はドライバ段のグリッドバイアスの差になります。
真空管もそうですが、半導体の特性にも相当なばらつきがあります。しかも、本機で使用する半導体(2SK30A)は、次段とが直結となっているにもかかわらずDCバランス調整を省略してしまっているため、かなり高い精度のペアが必要になります。選別回路は非常に簡単で、9Vの乾電池(006P)と1kΩの抵抗器とミノムシクリップがあればOKですので、是非、用意してください(下図)。
「定電流ダイオード(CRD)」は、初段FETの共通ソース側に2mA、ドライバ段6FQ7(6DJ8)段の共通カソード側に4mA、出力段の定電流回路に2mAのものを使いますが、特に初段に精度が要求されます。上図の回路を使って、テスターで(a)〜(b)間すなわち1kΩの抵抗器の両端電圧を測定すれば、定電流ダイオードのIdss特性が直読できます。2mAにできるだけ近くてしかも揃った2本を初段の各チャネルで使用し、ドライバ段の各チャネルには2本の合計値が約4mAになるようなセットを2組作って並列にして使用し、残りものから2本選んで出力段で使用します。出力段用は、1.5mA以上であれば問題ありません。10〜12本ほど買ってきてその中から8本を選べば、無駄なく、高精度なペアが確保できるというわけです。
2SK30AはYクラスのものを10本くらい買ってきます。3本の脚は、記号面に向かって左から「S-G-D」の順です。FETのIdssの測定は、上述した定電流ダイオードの測定と非常に良く似ています。FETは、ゲート(G)をソース(S)につないでしまうと、定電流ダイオードと同じ特性になります。おそらく、1.8mA〜2.4mAくらいの間にばらつくと思います。2mA以上のIdssのものから良く揃った4本を選び、そこから2本ずつペアを作ります。なお、この方法では、Idssは揃ってもgmまでは揃ってくれませんが、Idssが2%以内で揃っていればgmもだいたい近い値になってくれるので問題はありません。
定電圧ダイオードは、初段電源回路で24V〜25Vのものを2本、出力段の定電流回路で6V前後のものを2本使います。24Vの定電圧ダイオードの精度が回路の動作に与えるインパクトは相対的に低いですから選別しなくても大丈夫です。しかし、6Vの方はこの値が出力段のプレート電流を決定してしまいますので必ず選別してください。5.8V〜6.2Vの範囲が望ましいです。測定の方法は、定電流ダイオードの時と似ていますが、測定する部位が異なりダイオードの両端に生じる電圧ですから注意してください。
本機で使用する「抵抗器」のなかで、特に抵抗値の精度を確保したいのは、初段ドレイン抵抗(10kΩ)、ドライバ段プレート抵抗(47kΩ)、出力段定電流回路の抵抗(100Ω)です。安価なK級(許容誤差5%)の抵抗を本数を多目に購入し、そのなかから値のそろったものを選別したらいいでしょう。実は、選別という作業は、購入した部品の検査も兼ねています。ですから、高精度の抵抗器を購入された場合でも、測定はするようにしてください。
ドライバ段の動作条件は右図のようになります。1つのグラフに6DJ8と6FQ7の両方のEp-Ip特性をいれてあります。共有カソード側の定電流ダイオードの値が4mAであるため、1本あたりのプレート電流は自動的に半分の2mAに決まります。
6DJ8
6FQ7
6CG7Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接続 2 2G 2K H H 1P 1G 1K IS or IC 6DJ8を選んだ理由は、当初入手した6AH4GTがGE製の非常に背が低いかわいい球であり、しかもガラス面の印字がグリーンだったので、たまたま手許にあった小型のSYLVANIA製の6922(6DJ8と同等)のガラス面の印字が同じグリーンであったのと合わせてみよう、というばかばかしい動機ではじまったのでした。6DJ8族は、非常に低い内部抵抗とすぐれた直線性を持ち、本機のような低い電源電圧でも高い出力電圧が得られるということも選んだ理由のひとつです。
しかし、実装してみると、案の定、総合利得が高すぎたため、試しに6FQ7に差し替えてみたところ、手頃な利得になってくれたのでそのままにしてあります。当初は、6DJ8を使うつもりで設定したロードラインですが、このまま6FQ7に差し替えてもほとんど何の問題もないことがおわかりいただけると思います。6FQ7と同じ特性の6SN7GTも使えますし、ほぼ同特性の12AU7を使ってもかまいません。
ただし、6FQ7の入力容量(Cg-pおよびミラー効果)は6DJ8のそれよりもちょっと大きいため、初段〜ドライバ段で決定される超高域特性は若干ですが劣っていますし、6FQ7の方が内部抵抗が高い分、ドライバ段〜出力段で決定される超高域特性もまたやや劣っています。さらに、ドライバ段の利得が下がった分、初段が供給しなければならない出力電圧が高くなったため、総合的な歪みはわずかですが高くなってしまいました。6DJ8族はgmは極端に高いため、非常に発振しやすいことで有名です。実装に慣れていない場合は、12AU7や6FQ7/6CG7をお使いになることをおすすめします。
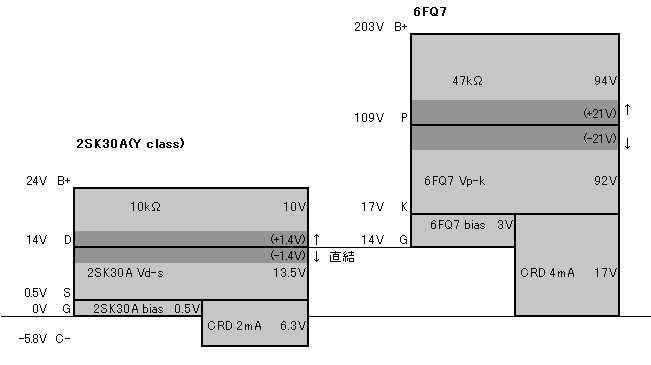
6FQ7を使用した場合、電圧利得はおおよそ15倍ですから、初段は、ピーク値で±1.4Vが取り出せなければなりません。初段の電源供給電圧は24V、定電流ダイオードによって決定される2SK30Aのドレイン電流は1mAですから、ドレイン負荷抵抗(10kΩ)によって生じる電圧降下は10Vになるので、6FQ7と直結になっている2SK30Aのドレイン電圧は、24V-10V=14Vになります。
直結となったドライバ段のグリッド電位は、初段の定電流ダイオードの値(2mA)と電源供給電圧(24V)とドレイン負荷抵抗(10kΩ)によって決定される、ドレイン電圧(14V)と同じになります。しかし、14Vになるはずのグリッド電位が変動したとしても、ドライバ段のプレート電流は定電流ダイオード(4mA)でのみ決定され、グリッド電位の影響を受けることはありませんから、この直結回路の動作は非常に安定しているといえます。
製作当時、6AH4GTという球については、(当初)Ep-Ip特性データが入手できませんでした(今は、インターネットで詳細なデータが入手できます)。わかっていたのは、
ぐらいです。しかし、これだけの情報があれば、おおよそのEp-Ip特性の見当をつけることができます。
- Ep=250V、Eg1=-23V、Ip=30mAのとき、
- rp=1.78kΩ、μ=8、gm=4.5であること、
- そのときの推奨負荷インピーダンスは5kΩらしいこと、
右図を参照してください。まず、Ep=250V、Ip=30mAのポイント(A点)におけるバイアスが-23Vで、そのときの内部抵抗(rp)が1.78kΩですから、A点を通るような、rp=1.78kΩの直線(本来は曲線)を引いてみます。ついでに、バイアスが-20Vと-26Vの時の直線(本来は曲線)も引いてみました。
次に、A点と同じIp=30mAで、バイアスが0Vのポイントを求めてみます。μが8ですから、23V×8=184Vとなるので、250V-184V=66VがB点です。一般に、バイアスが浅くなるにつれてμも若干増大するので、B点となるのはここよりもやや左寄りになります。
もうひとつ、別のアプローチもやってみましょう。Ep=0V、Ip=0V(つまり右下隅)を起点とした、rp=1.8kΩの直線も引いてみます。Eg1=0Vの特性曲線は、B点付近を通り、rp=1.78kΩの直線に近似していて、実際には弓なりな曲線になります。そういう見当をつけて引いてみたのがB'の曲線です。直線性の良い直熱3極管では太い黒線の角度に近くなり、直線性の悪い傍熱3極管では細い曲線のような傾向があります。
最後に、A点を通るような5kΩのロードライン(C)を引きます。いかがでしょう?これだけ情報が揃えば、動作条件が変わっても、おおよその設計ができるということがおわかりいただけたでしょうか。真空管データは、このような使い方ができるように、キーとなる動作ポイントをおさえて発表されています。なかには、Eg1=0Vのデータも補足されている場合が多く、これがわかればEg1=0Vのケースについてももっと正確に把握できます。
6AH4GTのEp-Ip特性データは、「私のアンプ設計マニュアル」Ep-Ip特性曲線特論中にあります。
OPTを使用した真空管プッシュプル回路は、本質的に直列ドライブです。信号ループが、「→出力管→出力管→OPT(1/2)→OPT(1/2)→元に戻って一周する」となっているからです。しかし、普通にみられるプッシュプル回路では、この信号ループとは別に「アース〜電源間」にも信号が混ざって流れるような2種類のループが混在した格好になっています。
さて、プッシュプル回路では共通カソード側はアースされるのが普通ですが、この共通カソードを交流的にアースしないようにすると、上記の「アース〜電源間」を通るループを遮断することができます。こうすることで信号は純粋に「→出力管→出力管→OPT(1/2)→OPT(1/2)→元に戻って一周する」ようになります。本機では、6AH4GTの共通カソード側にトランジスタを使った定電流回路を挿入しているので、信号は「アース〜電源間」にはほとんど流れません。信号が「アース〜電源間」に流れないということは、信号が電源のパスコンの中を流れないということをも意味します。
このような動作では、プッシュプルの片側がカットオフすることが許されなくなりますので、A1級動作しかできなくなり、最大出力はシングル動作の2倍以下ということになってしまいます。実際、6AH4GTはシングル動作で3W出せるのに、プッシュプル動作である本機の出力は4Wたらずしかありません。
さて、その6AH4GTですが、テレビ用途として開発され、親戚には6CK4や6BX7GTとその改良版6G-A4等があります。その用途としての性格から、直線性は意図的にやや悪くなるように設計されているものの、プレート電圧250V、プレート電流30mA時の内部抵抗が1.8kΩというのは銘球45と同じです。μは8くらいありますから、感度は45の2倍程度高いというわけで、パワーが小さいことを除けばオーディオ用途として使いやすい球のひとつにあげていいと思います。
6AH4GT Pin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 接続 G H - - P - H K そもそもこの球に着目したのは、冒頭にも述べたように浅野勇著「魅惑の真空管アンプ下巻」の'50シングルアンプで、この球がドライバとして使われていて、そこで「内部抵抗1.8kΩ」というデータを見つけたからです。試しにシングル動作をさせて試聴してみたところ、透明感があって、中域に充実感のあるキャラクターを持っていることがわかりました。直感的に「これはいける」と判断したわけです。いちばんうれしいのは、供給が豊富で安価であることです。
出力管の動作点は、理想的には、Ep=250V、Ip=30mA、RL=10KΩあたりなのですが、パソコン通信の知り合いの方がCRD-8を手ごろな値段で譲ってくださったので8KΩ負荷となりました。8KΩ負荷の場合は、Ep=230V、Ip=34mAあたりで電力効率がいちばん良くなりますが、残念ながらそれだけの電流を取り出すと電源トランス(TANGO LH-150)が相当に加熱します。本機のIpは30mA〜32mAですので、ロードライン上に若干の無駄が生じてしまい、電力効率はやや悪くなっています。バイアスは-21Vくらいですが、バラツキの大きい球ですので、-18V〜-23Vくらいの範囲になると思います。10KΩ負荷であればIp=30mAのままで最大出力は20%アップします。しかし、10kΩの出力トランスを使って、本機と同じトーンキャラクタになるかどうかは?です。
さて、全段差動という回路構成による改善効果は眼をみはるものがあります。左右の分離の良い、ソノリティの高いサウンドは、シングル・アンプではなかなか得られない世界です。また、低域のすわりの良さもまた独特のものがあります。これまでシングル・アンプ一本でやってきて、本機が生まれてはじめての真空管プッシュプル・アンプですが「こんな結果が出たのでは、もうシングル・アンプには戻れないかもしれない。」と思ったりもします。
本回路では、出力段のカソードが交流的にアースから切り離されています。この共通カソードとアースの間にコンデンサを挿入してカソードを交流的にアースしてしまったらどうなるでしょうか。本回路がねらったメリットがなくなり、ごく一般的なA級プッシュプル回路に近くなります。実験の結果では、カソードをコンデンサでアースすると、最大出力が増加し歪み率も若干低下します。しかし、本機独特の音場感や定位良さ、ソノリティの高さに蔭りが出ます。
ところで、この回路にはひとつ問題点があります。もし、プッシュプルの一方の球がだめになった場合、残ったもう1本の球に2本分のプレート電流が流れてしまうという問題です。カソード側に定電流回路が組み込まれているわけですから当然といえば当然ですが、厄介な問題です。これが6BX7GTや5998のように双3極管であればどうせ1本パーになるので気にしなくてもいいのですが、今のところ市場価格の安い6AH4GTならともかく、45や300Bのような貴重品ではそうはいきません。真空管メーリング・リスト(http://www.st.rim.or.jp/~idee/tubeML.html)でも話題になった問題です。現実には、一方の球がお釈迦になるとプッシュプル・ループが途切れてしまうため、音が出なくなりますので動作中であればすぐに気がつきます。通常のプッシュプル・アンプが、一方の球が駄目になってもなんとなく音が出続けてしまうのと対照的です。
2SK30Aの特性はほとんど水平なので、利得は「ドレイン負荷抵抗×gm」で求めることができます。2SK30Aのデータシートにはそのものズバリgmのデータがあるのですが、実測すると少し違うようなのです。下図は、左側がデータシート、右側が実測データです。
1mAのところを見ると、データシートでは1.5〜1.6ですが、実測では1.8〜1.9と大きな値になりました。初段はロードラインを使って求めた値が9倍でしたがこれを採用します。
ドライバ段の負荷をは、プレート負荷抵抗(47kΩ)と出力段のグリッド抵抗(300kΩ+VR約5kΩ)です。47kΩと305kΩの並列合成値は40.7kΩです。6FQ7の内部抵抗=10kΩ、μ=22として利得を計算すると17.7倍になります。
出力段の負荷インピーダンスは4kΩ、6AH4GTの内部抵抗=1.78kΩ、μ=8としてグリッド→プレート間の電圧利得を計算すると0.692倍(-3.2dB)5.54
使用したOPTはTANGO LH-150ですが、整流出力電圧が高いため、電源電圧のつじつまを合わせるためにはB電源の電圧を相当にドロップさせなければなりません。そこで、電源トランスの5Vの2次巻線を1次巻線(100V)に加えるというせこいことをやっています。これで、すべての2次巻線電圧が5%ダウンしますが、幸いヒーター電圧に目立った不足は生じませんでした。
さらに、トランジスタ・リプル・フィルタのところで電圧ドロップをさせたいのですが、ここで発生する熱をシャーシ内部にこもらせたくありません。そこで、左右2CH分のトランジスタのヒートシンクをアンプ上面に浮かせて取り付けることで効率良く放熱させることにしました(右の写真)。
シャーシ内部にこもった熱の出口は全部で3つあります。(1)シャーシを伝って外に放出される、(2)4個の直径1cmの穴から出る、(3)OPTが伏せ型なので、大きく穿った取り付け穴の隙間から出る、の3つです。また、セメント抵抗等発熱量の大きい部品の上方にはコンデンサや半導体等熱に弱い部品は配置しないようにしました。
本機では、多数の半導体を使用しています。ヒーターなどというもので積極的に熱を発生させて動作するのが真空管の宿命ですが、一方で半導体ほど熱に弱い素子もありません。そこで、設計段階でシャーシ内部の温度が0℃〜50℃に変化した場合の各FET、トランジスタ、ダイオードの温度特性をシミュレートして回路全体のドリフトの範囲と動作の安定を確認しています。
本アンプで失敗といえるのは、シャーシ(300mm×150mm×60mm)が小さく、電源トランスとOPTとが接近しすぎて、わずかですがリーケージによるハムを拾ったことです。電源トランスと出力トランスを、あと1cm離すだけでも全く違った結果になったと思いますが、そんなスペースはありません。もうひとつは、電源スイッチとヒューズを省略したことです。完成直後、早速事故を起こしました。電源スイッチがないのはほんとうに不便ですし、ヒューズがないのはとても危険です。このような設計は絶対にしないでください。
本機は、調整個所は2ヶ所あります。出力管プレート電流バランスの調整
各出力管のプレート電流値を揃えるには、出力トランスの直流抵抗による電圧降下を利用します。2つのプレート間にテスター(DCVレンジ)を当て、そこに生じる電圧が0.2V以下になるようにバイアスのボリュームを調整します。ちなみに、CRD-8の1次巻き線は揃っておらず、20Ωほどのアンバランスがあったので補正抵抗を入れてあります。
負帰還量の調整
負帰還回路の100Ωの半固定抵抗が0Ωの状態では無帰還になり、抵抗値を増加させてゆくにつれて負帰還がかかってゆきます。オーディオジェネレータ(発振器)とミリボルトメーターをお持ちの方は、出力信号が無帰還時の1/2くらいになるように調整すれば、現在、私が使っているのと同じ6dBの負帰還ががかります。もちろん、お好みに合わせて調整されたらいいでしょう。
測定器をお持ちでない方の場合は、以下の要領で同等の調整が可能です。まず、電源トランスのヒーター巻き線を流用して右図のような回路を作り、50〜60Hzで0.03〜0.1V位の交流信号を作り出します。50〜60Hzの交流を、オーディオジェネレーターの代用にしようというわけです。本機のようなプッシュプルアンプでは、50Hzという低い周波数であってもほとんどフラットな特性が得られていますので、正確な負帰還量の調整ができます。
8Ω/5W〜10Wの抵抗器を2個用意し、これをダミーロードとしてスピーカ端子につなぎます。負帰還回路の100Ωの半固定抵抗が0Ωの状態で入力端子から50〜60Hzの交流信号を入力し、出力側で1Vとなるように1kΩのボリュームを調整します。次いで、出力側の電圧が0.71Vになるように100Ωの半固定抵抗を調整すれば3dBの負帰還となり、0.5Vでは6dB、0.4Vでは8dB、0.32Vでは10dBになります。
初段 ドライバ段 出力段 使用真空管(Tubes) 2SK30A(Y) 6DJ8→6FQ7 6AH4GT Sylvania 駆動方式(Bias) 定電流 前段と直結+定電流 定電流 電源供給電圧(Eb) 24V 203V 264V プレート電圧/ドレイン-ソース間電圧(Ep/Eds) 13.5V 91.5V 237.5V プレート電流/ドレイン電流(Ip/Id) 1mA×2 2.0mA×2 30mA×2 負荷抵抗(RL) 10kΩ×2 47k×2 8kΩp-p(推奨10kΩp-p) 出力トランス(OPT) - - TANGO CRD-8(またはCRD-10)
6DJ8 6FQ7/6CG7 6AH4GT Base MT9pin MT9pin US Heater 6.3V×0.365A 6.3V×0.6A 6.3V×0.75A Cin 3.3pF/6.0pF 2.4pF/2.4pF 7.0pF Cout 1.8pF/2.8pF 0.34pF/0.24pF 1.7pF Cgp 1.4pF/1.4pF 3.6pF/3.8pF 4.4pF 最大定格 Ebb max 550V - - Ep max 130V 330V 500V Pp max 1.8W×2 4.0W×2(5.7W/total) 7.5W Rg1 max 1MΩ 2.2MΩ - 動作例 Ep 90V 250V 250V Eg1 -1.3V -8.0V -23V Ip 15mA 9.0mA 30mA gm 12.5 2.6 4.5 rp 2.64kΩ 7.7kΩ 1.78kΩ μ 33 20 8 Pin Connection 2P(1),2G(2),2K(3),H(4),H(5),
1P(6),1G(7),1K(8),IS(9)2P(1),2G(2),2K(3),H(4),H(5),
1P(6),1G(7),1K(8),NC(9)G(1),H(2),NC(3),NC(4),
P(5),NC(6),H(7),K(8)
裸利得(RawGain)・・・ドライバ段=6DJ8のとき 33.3dB NFB=0dB 最終利得(Gain)・・・ドライバ段=6DJ8のとき 27.3dB NFB=6.0dB 周波数特性(FrequencyResponse) 10Hz〜140kHz +0dB/-1dB クロストーク(CrossTalk)・・1999.7.31追加 80dB(R to L)、77dB(L to R) 10Hz〜100kHz 出力(OutputPower) 4.2W 5%歪み at 1kHz 歪み率(Distortion)・・1999.7.31更新 0.07% 0.1W at 1kHz 0.24% 1W at 1kHz 1.2% 3W at 1kHz ダンピング・ファクタ(D.F.) --- 10Hz〜30kHz 残留雑音(Noise) 0.26mV(L)、0.47mV(R) A補正なし 全消費電力 75W AC100V
回路図へ (1999.7.31, 2005.9.3)
トランス類は見てのとおり、PTが中央上、2つのOPTが左右下隅に見えます。B電源ですが、シリコンダイオードを経た整流出力は、中央下の電解コンデンサにはいります。中央下に見えるラグ板は、初段用のマイナス電源回路です。トランジスタ・リプル・フィルタ関連の回路は、シャーシ上面の放熱器付きの高耐圧トランジスタと、左右にあるOPTの手前に見える放熱器なしの2つの高耐圧トランジスタとで構成されています。
左右のシャーシ壁面に上下に長いラグ板がありますが、向かって上半分が出力段の定電流回路、下半分が初段2SK30Aの差動回路です。出力段の定電流回路のトランジスタは、ラグ板すぐそばのシャーシ壁面に密着させています。
ドライバ管は、出力管とOPTとに挟まれた格好になっているため、入力RCAピンジャックをはいった信号は、シャーシ壁面にある初段から中央にあるドライバ管を経て、上面に並んでいる出力管にはいり、ドライバ管をまたいでOPTに至ります。OPTを出たら、すぐそこは出力端子です。
出力端子と初段とは目と鼻の先にあるため、負帰還回路は最短の配線で済んでいます。下面両端に見えるモールドタイプの可変抵抗器が負帰還量調整用です。
 全段差動の庭に戻る
全段差動の庭に戻る 情熱の真空管に戻る
情熱の真空管に戻る